受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
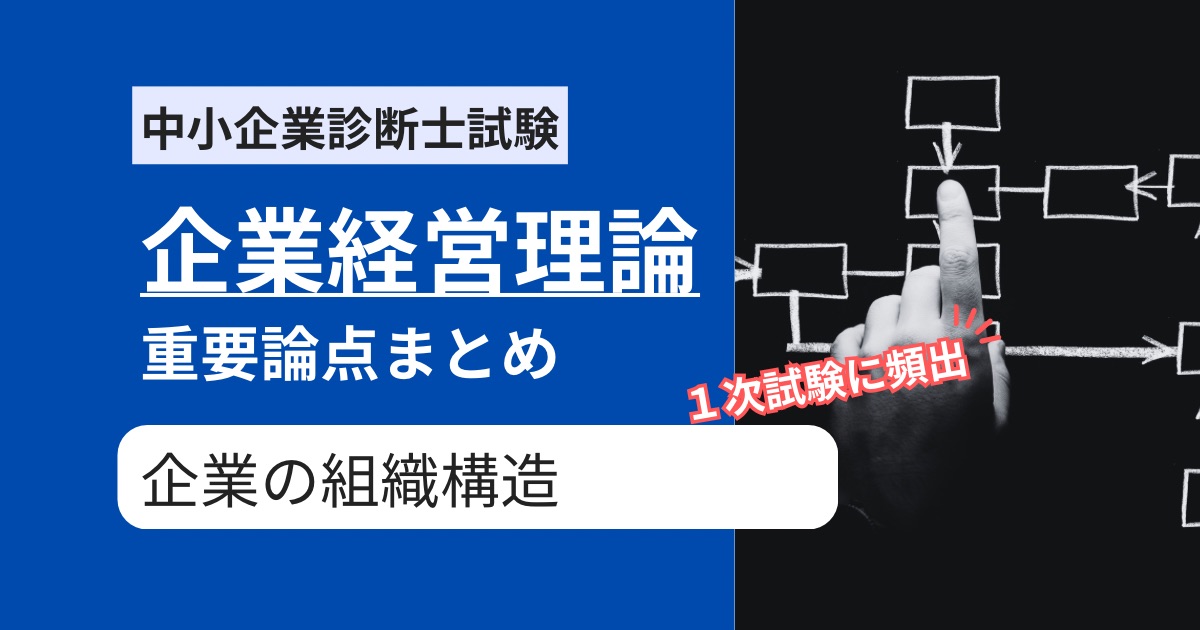
中小企業診断士試験の一次試験(企業経営理論)によく出る、組織構造に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
企業経営理論全般に言える話ですが、用語の暗記だけでは解答が難しく、より深い理解が求められます。また、問題文に抽象的な表現が多いので、ある程度の慣れが必要です。
過去問を繰り返し解き、問題文に慣れ、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例Ⅰで、組織や人事面の課題として組織構造が問われます。
直接、用語の知識が問われるのではなく、事例企業に対して問題・課題の指摘、課題に対する具体的な助言やその理由・目的を問われます。
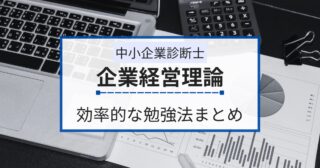
分業化と同じ意味で、特定の業務ごとに役割が分割された状態のこと
特定業務の知識や能力の習熟が行えノウハウの蓄積が可能となる。
各組織のメンバに与えられる権限の大きさが職務に相応し、それと同じ責任が負わされなければならないというもの
1人の上司が指揮監督できる部下の人数のこと
統制範囲とはスパンオブコントロールとも呼ばれ、部下の人数が管理の幅を超えると、管理効率が低下する。
| 統制範囲 | 内容 |
|---|---|
| 狭い(改造型) | 意思決定が遅い 専門職向き |
| 広い(フラット型) | 中間者のストレスが大きくなる 単純作業向き |
組織のメンバは1人の上司からのみ命令を受けること
経営者は、ルーティン業務の処理を下位レベルの者に委ね、例外的な業務(戦略的意思決定や非定型的意思決定)に専念する
| 定型的意思決定 | 決まった手順により行うことができる業務的意思決定 |
|---|---|
| 非定型的意思決定 | 結果が不確定で、既存の手順に頼ることができない戦略的意思決定 |
定型的意思決定に忙殺され、非定型的意思決定が後回しになることを、計画におけるグレシャムの法則と呼ぶ。
個々の機能(人事、営業、製造、開発、経理、財務など)単位の組織
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 専門性の発揮 規模の経済が発揮される トップに権限が集中することで、トップへ情報集約される | 意思決定に遅れが出る 組織内の人事交流が停滞する マネジメント層が育ちにくい 各部門ごとの利益責任が不明確ああ |
事業部(製品・サービス・地域・顧客ごと)単位の組織
| メリット | デメリット |
|---|---|
| トップが戦略的意思決定に専念できる 意思決定が早い マネジメント層の育成が比較的容易 市場変化に柔軟な対応ができる M&Aしやすい | 職能が各事業部で重複する 事業部単位での利益追求にこだわり視野が狭くなる 事業部間の競争によるセクショナリズムが起きやすい |
事業部制組織の独立採算制をさらに高め、独立した企業に近い組織
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 事業単位の収益性が徹底される | 本社のコントロールが効かなくなる 事業間シナジーの追求が難しい 事業再編が難しい |
横断型(格子型)の組織で機能別組織と事業部制組織のいいとこ取り
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 人的資源の共有が容易 情報共有が迅速に行える 環境の不確実性に対応し易い | ワンマンツーボスシステムとなり組織内コンフリクトが起き易い 命令統一性の原則に反し、責任の所在が不明確となる |
組織の起業から成熟までの過程を4つ段階に分類する。
| ライフサイクル | 段階 |
|---|---|
| 創業期 | 起業者段階 創始者の創造性や革新性が重視され、管理活動は軽視される |
| 成長前期 | 共同体段階 インフォーマル非公式なコミュニケーションが中心となる |
| 成長後期 | 公式化段階 労務、経理、人事などさまざまな規則が導入され、組織が官僚的になる |
| 成熟期 | 精巧化段階 組織の分割、プロジェクトチーム作成など柔軟性を高める |
職務が高度に専門化され効率を追求した組織構造
規則の徹底が求められることで、職務遂行に対する主体性が低くなるなどデメリットが生じること
ベンチャー企業が直面する3つ(川、谷、海の順)の関門
「基礎研究 → 実用化」の段階で発生する関門
基礎研究を市場のニーズに沿った実用化に結び付けられるかどうかという関門。
「実用化 → 事業化」の段階で発生する関門
実用化された製品に対し、資金や人材などの資源不足になり直面する関門。
「事業化後」の段階で発生する関門
事業化後に市場で激しい競争に晒される関門。
組織変革の基本的なプロセスについて。
組織の発展は、安定した漸次的進化過程と別の段階に飛躍する革新的変革過程が交互に組み合わさる
| 過程 | 組織の発展 |
|---|---|
| 漸次的進化過程 | 安定した段階で継続的な改善、積み重ねを行う 低次学習 |
| 革新的変革過程 | 組織が別の段階に移行する不連続な変化をする 高次学習 |
| 低次学習 | 既存の枠組みの中で行う修正、活動(シングルループ学習) |
|---|---|
| 高次学習 | 組織全体に影響を与える、既存の枠組みを超えた学習(ダブルループ学習) |
組織変革が必要にも関わらず行えない理由として、以下のような要因があげられる。
変革をする場合には、現状にとどまる限り発生しない埋没コストが発生し、この埋没コストが変革への抵抗要因となる
埋没コストとは、既に投資したにも関わらず回収不能なコストのこと。サンクコストとも呼ばれる。
ある新規事業に1,000万円の設備投資をしたが、赤字続きのためこの事業を中止した場合、設備投資の1,000万円は回収不能となり埋没コストとなる。この埋没コストに囚われすぎると、誤った意思決定をしてしまうことになる。
既存のビジネスに関係のない情報は排除される傾向にある
既存のビジネスが満足のいく利益を得ている場合、今より優れたものへの探求や情報収集は疎かになる。
業績が悪化しても、狭視点的な思考により変革が妨げられる
以下のような狭視点的な考えが働き変革の妨げとなる。
組織変革の遂行には、「必要性の認識」「変革案の創造」「変革の実施と定着のプロセスが必要となる
よりリッチな情報、つまり現場の生の情報を経営者が認識する必要がある。
革新的なアイディアを組織で共有する必要がある。
| 暗黙知 | 文字や言葉で表現できない主観的な考えノウハウといった知識 |
|---|---|
| 形式知 | 文書や言葉で表現可能な客観的な知識 |
変革に伴う組織内の争いへの対処が必要となる。
中小企業診断士 企業経営理論に頻出の、組織構造の覚えるべき5つのポイントをまとめました。
ここでまとめた内容以外にも、出題される用語や論点はたくさんあるので、過去問を繰り返し解き応用力を養う必要があります。
また、企業経営理論の内容は2次試験の事例問題でも関連する用語や知識が必要になります。直接用語の意味を問われる問題は出題されませんが、企業経営理論の知識を前提として、事例企業の診断・助言をする必要があるため、用語の意味を人に説明できるレベルが求められます。
企業経営理論の効率的な勉強方法については別記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
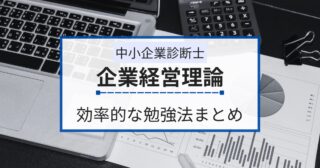
コメント