受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
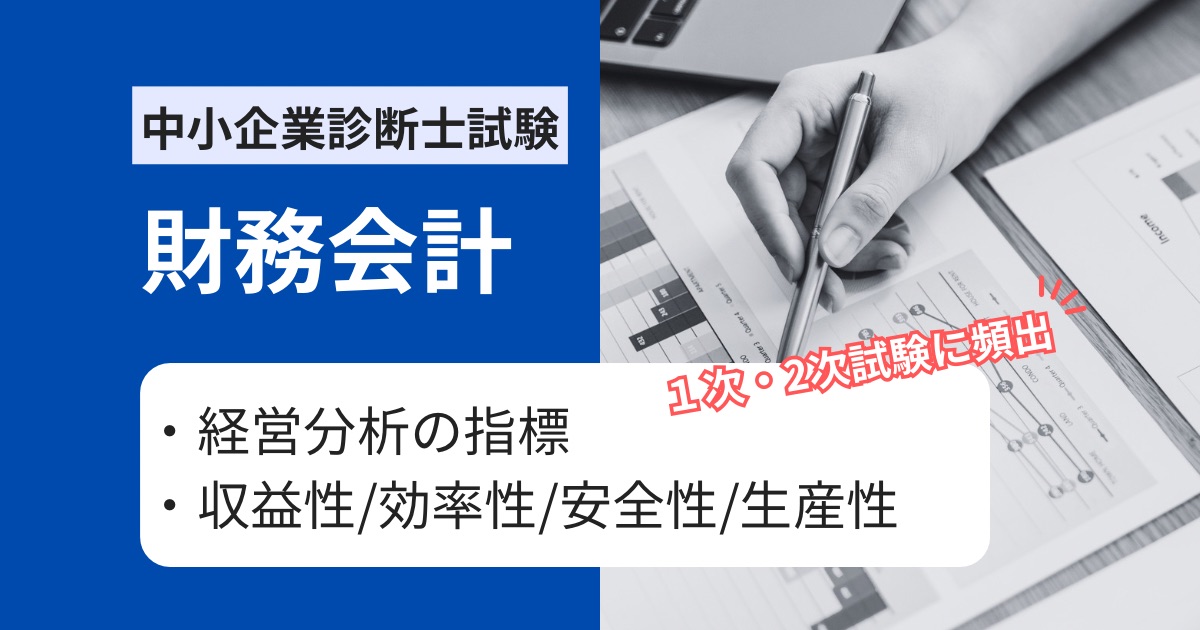
中小企業診断士試験の1次試験の財務会計に頻出の用語を知りたいと思っていませんか。
ここでは、財務会計に頻出の経営分析に用いる指標と式の覚え方や優劣についてまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに)
頻出論点の頭の整理に活用いただければと思います。
毎年、数問出題される頻出論点です。
各指標値は計算問題として出題されるので、式と意味は暗記が必須です。過去問や問題集を繰り返し解き、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例Ⅳで、財務会計の課題が扱われます。
設問1で、事例企業の経営分析について良い指標、悪い指標を必ず問われます。計算式の暗記はもちろんですが、なぜ値が良いか悪いかまで問われるので、指標の意味も理解する必要があります。
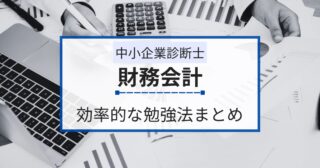
経営分析に用いる、基本的な用語とその内容をまとめます。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 総資本 | 純資産 + 負債 |
| 経営資本 | 流動資産 + 固定資産 – 建設仮勘定 – 投資等その他資産 |
| 自己資本 | 純資産 – 新株予約権 – 非支配株主持分(連結) |
| 事業利益 | 営業利益 + 受取利息・配当金 (財務活動による成果も含めた利益) |
| 金融費用 | 支払利息 + 社債利息 (他人資本による資金調達コスト) |
経営分析に用いる指標は、財務諸表(BSとPL)の情報を用いて分析(計算)を行います。財務諸表の内容も合わせて覚えるようにしましょう。
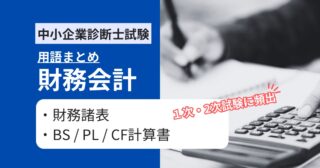
収益性分析は、投資に対し、利益をどれだけ得られるかを分析するもの。
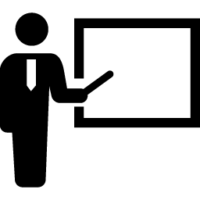
各指標の計算には、原則として期中平均の値を用います。試験問題で、1期分の財務諸表しか与えられない場合は期末の値を用います。
投資(investment)に対しどれだけ利益(return)があったかを表す、企業の収益性を表す指標
値は、高い方が望ましい。(小さな資本で大きな利益が得られることになる)
| 収益性分析指標 | 式 |
|---|---|
| 総資本経常利益率(%) | $$\frac{経常利益}{総資本}\times100$$ |
| ROA・総資本事業利益率(%) | $$\frac{事業利益}{総資本}\times100$$ |
| 経営資本営業利益率(%) | $$\frac{営業利益}{経営資本}\times100$$ |
| ROE・自己資本利益率(%) | $$\frac{当期純利益}{自己資本}\times100$$ |
「求めたいものの左側」が分母に来ると覚えればOK。
例えば、総資本(A)経常利益率(B)であれば $$\frac{B}{A}$$ となる。
売上高に対する利益の割合
値は、高い方が望ましい。
| 収益性分析指標 | 式 |
|---|---|
| 売上高総利益率(%) | $$\frac{売上総利益}{売上高}\times100$$ (粗利益率とも呼ばれる、売上高に占める利益の割合) 例) コンビニ:30% 商社:1〜2% |
| 売上高営業利益率(%) | $$\frac{営業利益}{売上高}\times100$$ |
| 売上高経常利益率(%) | $$\frac{経常利益}{売上高}\times100$$ |
| 売上高当期純利益率(%) | $$\frac{当期純利益}{売上高}\times100$$ |
「求めたいものの左側」が分母に来ると覚えればOK。
例えば、売上高(A)総利益率(B)であれば $$\frac{B}{A}$$ となる。
売上高に対する費用の割合
値は、低い方が望ましい。
| 収益性分析指標 | 式 |
|---|---|
| 売上高売上原価比率(%) | $$\frac{売上原価}{売上高}\times100$$ (売上原価:期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 – 期末商品棚卸高) |
| 売上高販管費比率(%) | $$\frac{販管費}{売上高}\times100$$ |
| 売上高人件費比率(%) | $$\frac{人件費}{売上高}\times100$$ |
| 売上高金融費用比率(%) | $$\frac{金融費用}{売上高}\times100$$ |
回転率、回転期間で資産の使用効率を分析する
回転率の値は、基本的には高い方が望ましい。
| 効率性分析指標 | 式 |
|---|---|
| 総資本回転率(回) | $$\frac{売上高}{総資本}\times100$$ (総資本あたりの売上高を表す。) |
| 経営資本回転率(回) | $$\frac{売上高}{経営資本}\times100$$ (本来の事業活動で得た資本(経営資本)で、どれだけ売上高をあげたか表す。) |
| 売上債権回転率(回) | $$\frac{売上高}{売上債権}\times100$$ (この指標が高いと、債権回収状況が良好であることを表す。) |
| 棚卸資産回転率(回) | $$\frac{売上高}{棚卸資産}\times100$$ (この指標が高いと、在庫の消化が良く在庫(棚卸資産)管理が適切に行われていることを表す。) ・製品(製造業)→原価 ・商品(流通業)→原価 ・仕掛品→原価以外 ・原材料→原価以外 |
| 有形固定資産回転率(回) | $$\frac{売上高}{有形固定資産}\times100$$ (この指標が高いと、機械設備などの有形固定資産の稼働率がよく、機械設備が有効に使われていることを表す。) |
| 買入債務回転率(回) | $$\frac{当期商品仕入高}{買入債務}\times100$$ (この指標は、仕入代金の支払い速度を表す。高い低いで良い悪いを表すわけではない。) |
| 売上債権回転期間(日) | $$\frac{受取手形+売掛金}{1日当たり平均売上高}$$ $$\frac{365日}{売上債権回転率}$$ (売上債権を回収するのにかかる日数。) |
| 棚卸資産回転期間(月) | $$\frac{棚卸資産}{1ヶ月当たり平均売上高}$$ $$\frac{12月}{棚卸資産回転率}$$ (棚卸資産として滞留する日数。) |
基本的には「○○回転率」の「○○」が分母、「売上高」が分子に来る。買入債務回転率のみ分子が「当期商品仕入高」となる。
回転期間については、それぞれ暗記が必要。
企業の短期的な支払い能力を分析する指標
短期安全性の値は、高い方が望ましい。
| 短期安全性指標 | 式 |
|---|---|
| 流動比率(%) | $$\frac{流動資産}{流動負債}\times100$$ (1年以内の支払う必要がある流動負債に対し、1年以内に現金化できる流動資産がどれだけ確保されているかを表す。) ※少なくとも100%以上、200%以上が望ましい |
| 当座比率(%) | $$\frac{当座資産}{流動負債}\times100$$ (流動比率よりも、回収可能性の高い資産で計算するため、企業の支払い能力をより厳格に評価する指標。) ※当座資産=現金/預金 + 受取手形 +売掛金 + 有価証券 ※貸倒引当金は控除する |
| インタレストカバレッジシオ(倍) | $$\frac{事業利益}{金融費用}$$ (本業の利益(営業利益)と財務活動での利益が、支払い利息などの金融費用の何倍であるかを表す指標。) 単位は「倍」となる。 |
企業の長期的な資産、資金調達を分析する指標
長期安全性の値は、低い方が望ましい。
| 長期安全性指標 | 式 |
|---|---|
| 固定比率 | $$\frac{固定資産}{自己資本}\times100$$ 長期的な固定資産が自己資本により賄えているかを表す。値は低いほど(固定資産 < 自己資本)安定的な設備投資がされていることになる。 |
| 固定長期適合率 | $$\frac{固定資産}{自己資本+固定負債}\times100$$ 長期的な固定資産が長期資本により賄えているかを表す。 |
資本調達において、他人資本と自己資本の比率から依存度を評価する指標
| 資本調達構造指標 | 式 |
|---|---|
| 自己資本比率(%) | $$\frac{自己資本}{総資本}$$ (総資本に占める返済の必要のない自己資本の割合を示す。一般的には高い方が望ましいが、業者や事業内容によるので一概に高ければ良いというわけではない。) 国内例) 大企業平均:約40% 中小企業平均:約25% 医薬品業界:60〜80%ほど スーパーゼネコン:20〜30%ほど 銀行業界:9%ほど |
| 負債比率(%) | $$\frac{負債}{自己資本}$$ (他人資本と自己資本のバランスを見る指標で、値は、一般的に低いほど安全性が高い。) |
安全性分析の指標と式にはあまり法則性がないので暗記が必要。それぞれの指標の意味を理解すると覚えやすい。
生産の効率を表す指標
生産性分析の値は、高い方が良い。
| 生産性分析指標 | 式 |
|---|---|
| 労働生産性 | $$\frac{産出量}{労働力}$$ |
| 資本生産性 | $$\frac{産出量}{資本}$$ |
| 労働生産性(円/人) | $$\frac{付加価値額}{従業員数}$$ |
生産性の指標は、 $$\frac{産出量}{投入量}$$ の関係となる。
付加価値額とは、原材料に対し新たな価値を産み出したもののこと。
付加価値額=経常利益+労務費+人件費+支払利息割引料ー受取利息配当金+賃借量+租税公課+減価償却
経営分析に用いる各指標値について、高い方が良好か低い方が良好かを以下にまとめます。
| 指標値 | 比較して良好 |
|---|---|
| 〜利益率 | 高い |
| 〜回転率 | 高い ※買入債務回転率はバランスによる |
| 〜回転期間 | 短い |
| 短期安全性指標 | 高い |
| 長期安全性指標 | 低い |
| 自己資本比率 | 高い ※業界による |
| 負債比率 | 低い ※業界による |
| 生産性 | 高い |
経営分析の指標の計算は、1次試験・2次試験ともに頻出です。
計算式の暗記は必須で、それぞれの指標の優劣が答えられる必要があります。繰り返し過去問や演習問題を解き応用力を高めましょう。
特に、2次試験でも経営分析の各指標は毎年必ず出題されます(事例Ⅳの設問1に毎年出題される)。2次試験では事例企業への助言に最適な分析指標を、自分で選ぶ必要があります。そのため、計算できるだけでなく各指標の意味もしっかりと理解する必要があります。
また、事例Ⅳの計算には電卓の使用が必須です。中小企業診断士の試験にオススメの電卓の選び方と使い方は、別記事で詳細解説しているのでこちらも参考にしてください。
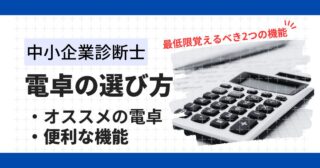
コメント