受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
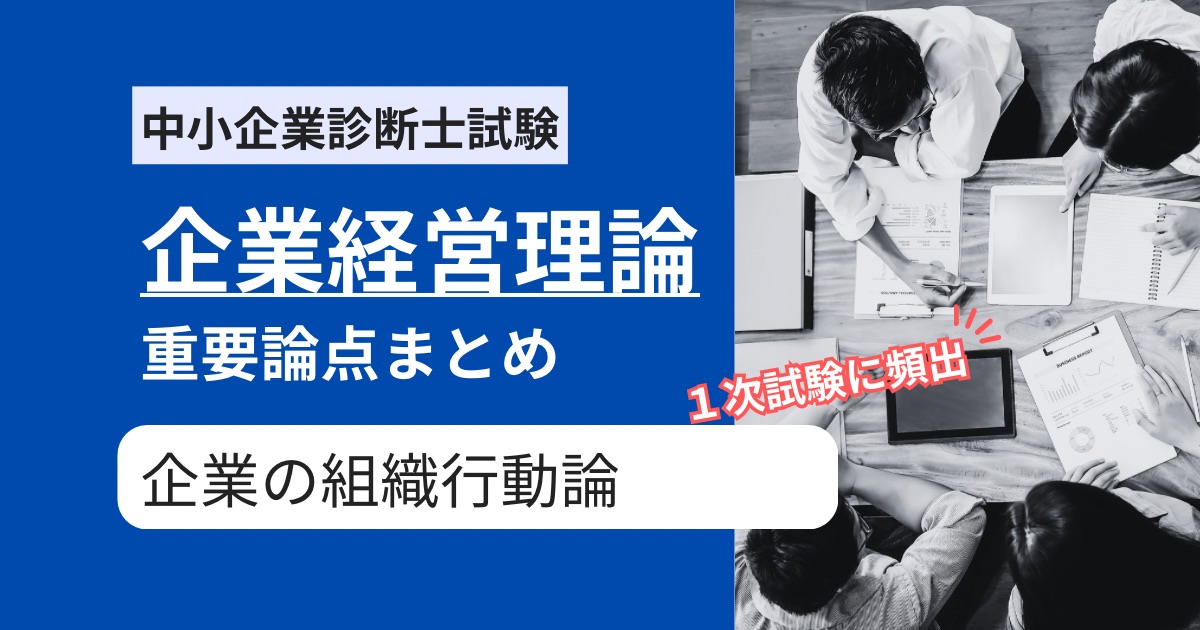
中小企業診断士試験の一次試験(企業経営理論)によく出る、組織行動論に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
企業経営理論全般に言える話ですが、用語の暗記だけでは解答が難しく、より深い理解が求められます。また、問題文に抽象的な表現が多いので、ある程度の慣れが必要です。
過去問を繰り返し解き、問題文に慣れ、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例Ⅰで、組織や人事面の課題として組織行動が問われます。
用語の知識が問われるのではなく、事例企業に対して具体的な策やその理由・目的を問われます。
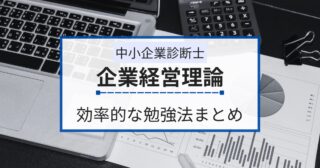
個人を行動に駆り立てるのは何かに関する理論
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 内容理論 | 何によって動機付けられるか |
| 過程理論 | どのように動機づけられるのか |
| 内発的動機づけ理論 | 自分自身の内部からの動機づけ |
人は何によって動機付けられるかを示した理論
人間の持つ欲求を、低次から高次に5段階に分けたもの
| マズローの欲求段階説 | 内容 |
|---|---|
| 自己実現の欲求(高次) | 自己の向上を図りたい |
| 尊重の欲求 | 他社から尊敬されたい |
| 所属と愛の欲求 (社会的欲求) | 集団に適合し充足した状況を求める |
| 安全の欲求 | 安定した状況を求める |
| 生理的欲求(低次) | 本能的な欲求 |
低次から高次にかけて不可逆的であるのが特徴。高次の欲求を満たすためには、低次において改善が必要とされる。
マズローの欲求段階説の拡張版
| アルダファーのERG理論 | 内容 |
|---|---|
| Existence | 基本的な存在の欲求 |
| Relatednss | 人間関係にかかわる関係の欲求 |
| Growth | 人間らしく生きたい成長の欲求 |
マズローの欲求段階説との違いは、アルダファーのERG理論は可逆的であり、同時に存在することとされている。
個人の人格は、未成熟から成熟へ向かおうとする欲求を満たすことで変化するというもの
自己実現欲求を満たすためには職務拡大(ジョブエンラージメント)や感受性訓練が必要とされている。
職務拡大(ジョブエンラージメント)
仕事の量的な範囲拡大
X理論に基づく人間は低次の欲求しか持たないが、高次欲求を満たすにはY理論に基づく人間観で動機付けが必要とされる
| マクレガーのX理論・Y理論 | 内容 |
|---|---|
| X理論 | 人はもともと仕事が嫌い 人は管理されないと能力を発揮しない 命令されることを好む 責任は持ちたくない |
| Y理論 | 人はもともと仕事が嫌いというわけではない 人は目標を達成することで得られる報酬によって献身的に働く 条件次第で自ら責任を持つ |
Y理論に基づく動機付けとして、MBO(目標管理制度)、権限委譲、職務拡大が有効とされる。
高次欲求を満たすためには、職務に対する動機づけが必要であるという理論
「ハーズバーグの動機づけ=衛生理論」における動機付けの方法としては、職務充実(ジョブエンリッチメント)があげられる。
職務充実(ジョブエンリッチメント)
仕事の責任・権限の(質的な)拡大
人はどのように動機づけられるのかを示した理論
| 過程理論 | 概要 |
|---|---|
| 強化説 | 適切な報酬を適宜受け取ることで動機づけられる |
| 公平説 | 報酬を他人と比較し、主観的な公平・不公平感で動機づけられる |
| 期待理論 | 期待×優位性=動機づけの強さ |
明白な報酬や業績のないものに対し、自分自身の内部から動機づけをするという理論
具体的には以下のようなものがあげられる。
また、以下の5つの特性がある場合、内発的動機づけられやすいとされる。
集団力学、グループダイナミクスとも呼ばれ、人が複数人集まった集団では、そこならではの力学が発生するため、組織運営においてそれらを理解する必要がある。
集団の団結の度合い
以下の度合いが高いと集団の凝集性は高まる。
集団で意思決定すると、短絡的な決定となる現象
集団の凝集性が高いと発生しやすく、自集団に対する過剰評価、閉鎖的な発想、内部の圧力が影響する。
| グループシフト | 結論が極端なものとなる |
|---|---|
| リスキーシフト | 結論が極端にリスクの高いものとなる |
集団浅慮が悪い方向に働いた例として、以下があげられる。
イェール大学の実験心理学者。
グループシンクの研究者。
個人内、個人間、組織内、組織間で発生する、目標や行動の違いによる対立や葛藤のこと
否定的な意味合いでとらえられるが、組織の活性化や新しい価値の創造に貢献するとされ、積極的な活用が必要。コンフリクトは以下のような場合に発生する。
リーダーシップとは、経営目的を達成するために、周りの人々に影響力を及ぼすこと、とされる。リーダーシップとマネジメントはよく似ているが、機能としては、リーダーシップは「変革を推し進める機能」、マネジメントは「効率的に組織運営する機能」とされる。
ハーバード大学ビジネススクール名誉教授
リーダーシップ論の権威として世界的に知られる人物。著書に「パワー・イン・マネジメント」「ザ・ゼネラル・マネジャー」などなど120カ国語以上に翻訳されている。
リーダーの行動パターンから類型化を図り、合理的に優れたリーダーシップを探る理論。
リーダーシップを3つの類型に分類し、民主型リーダーシップが最も優れるとしている
リーダーシップを以下の3つの類型に分類する。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 民主型リーダーシップ | 集団で討議し決定する。リーダーはそれを支援する。 |
| 独裁型リーダーシップ | リーダーが全てを決定する。 |
| 放任型リーダーシップ | 個人が自由に決定する。 |
リーダーの行動を構造造りと配慮の2タイプに分類し、構造造りと配慮の双方に関心の高いリーダーが優れるとする
リーダーシップの行動を、以下の2つのカテゴリーに分類する。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 構造造り(タスク) | 目標に向けた部下との役割定義 |
| 配慮(人) | 部下への気配り、尊重 |
リーダーシップを、従業員志向型と生産志向型に分類し、従業員志向型のリーダーが好ましいとしている
リーダーシップ行動として、以下の2つに分類した。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 従業員志向型 | 部下との人間関係を重視する。 |
| 生産志向型 | 仕事の技術やタスクを重視する。 |
「P(Performance) 目標達成機能」と「M(Maintenance) 集団維持機能」の2つに分類しP・M共に機能が強いリーダが理想的なリーダーシップであるとするもの
日本の社会心理学者である三偶二不二らによって提唱されたリーダーシップ論。グループダイナミクスの観点からリーダーシップを考えたもの。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| P(performance) | 目標達成機能、タスク型 |
| M(maintenance) | 集団維持機能、配慮(人間関係)型 |
リーダーの置かれている状況により、有効なリーダーの行動スタイルを探るの理論。
統制のしやすさで考え、リーダーの取るべきスタイルとして仕事中心型か従業員中心型の2タイプを定義している
| スタイル | 統制のしやすさ |
|---|---|
| 仕事中心型(機械的) | 極端な場合(統制がしやすい or しにくい)に効果的である |
| 従業員中心型(有機的) | 曖昧な場合(統制のしやすさが中程度)に効果的である |
リーダの置かれている状況(統制のしやすさ)として、リーダーとの人間関係が良好か、仕事内容が明確か、リーダーの権限の強さの3つの要因でとらえている。
フィードラー理論は、自らのスタイルを変えないリーダーを前提としている。
リーダーは必要な道筋を示し、目標達成を助けることとしている
パス・ゴール理論は、自らのスタイルを状況に応じて変えることができるとしている。
中小企業診断士 企業経営理論に頻出の、組織行動論の覚えるべき重要理論をまとめました。
ここでまとめた内容以外にも、出題される用語や論点はたくさんあるので、過去問を繰り返し解き応用力を養う必要があります。
また、企業経営理論の内容は2次試験の事例問題でも関連する用語や知識が必要になります。直接用語の意味を問われる問題は出題されませんが、企業経営理論の知識を前提として、事例企業の診断・助言をする必要があるため、用語の意味を人に説明できるレベルが求められます。
企業経営理論の効率的な勉強方法については別記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
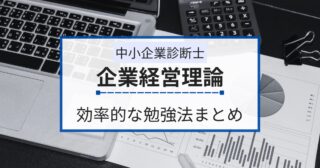
コメント