受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
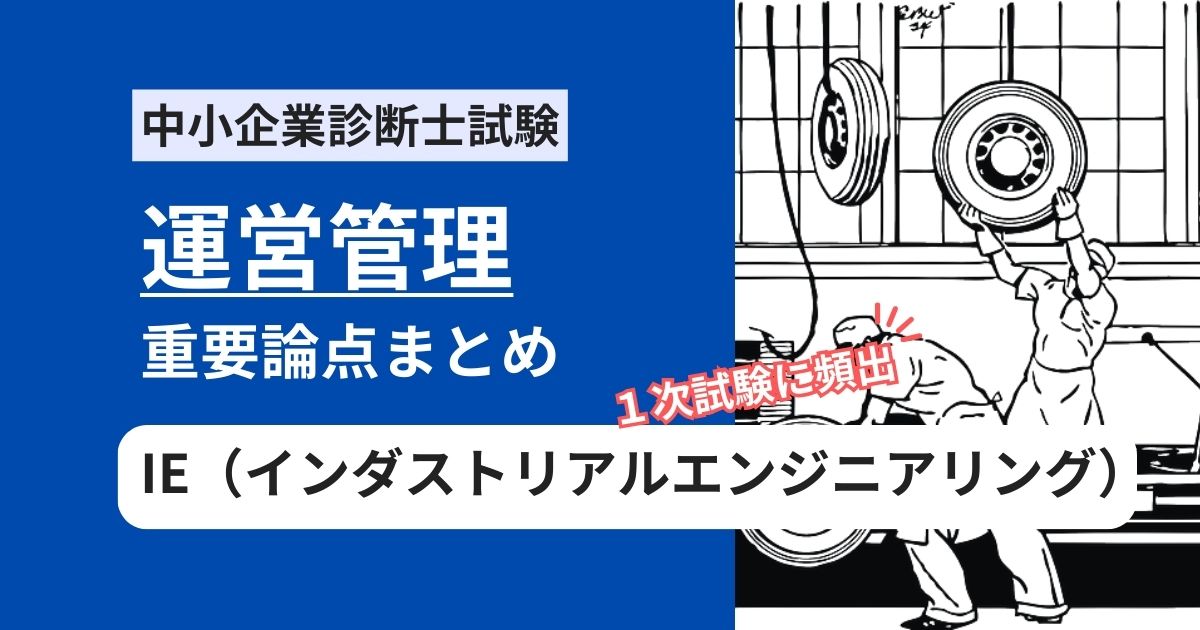
中小企業診断士試験の1次試験(運営管理)によく出る、IE(インダストリアルエンジニアリング)に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問は出題されている頻出論点です。
計算問題や図表問題も出題されるので、過去問を繰り返しチェックしましょう。特に計算問題は、単純な問題が多いので確実に回答できるようにしましょう。
各用語が直接問われることはないです。
ただし、このへんの用語を理解した前提で事例問題が問われます。ので、1次試験でしっかり知識を貯えておく必要があります。
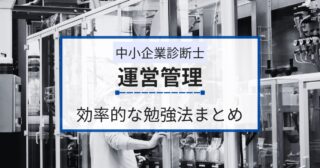
IEとは経営工学のことで、経営目的を定め、それを実現するために、環境と調和を図りながら、人、物、金、及び情報を最適に設計し、運用し、統制する工学的な技術・技法の体系
IE(インダストリアルエンジニアリング)は、工場の生産活動における改善の土台となっているもの。
IEでは、作業研究として方法研究と作業測定の以下の体系を構成する。
| IE(作業研究) | 方法研究 | 工程分析 |
|---|---|---|
| 動作研究 | ||
| 作業測定 | 稼働分析 | |
| 時間研究 |
工程図記号などを用いて、工程や工程間の効率性を調査・分析すること。
| 工程分析 | 単純工程分析 | |
|---|---|---|
| 詳細工程分析 | 製品工程分析 | |
| 作業者工程分析 | ||
| 流れ分析 | 流れ線図 | |
| 単純工程分析 | ||
| 多品種工程分析 | ||
| フロムツーチャート | ||
| 工程 | 名称 | 記号 | 作業者 |
|---|---|---|---|
| 加工 | 加工 | 作業 | |
| 運搬 | 運搬 | 移動 | |
| 停滞 | 貯蔵 | 手待ち | |
| 滞留 | |||
| 検査 | 数量検査 | 検査 | |
| 品質検査 |
ここに記載している工程図記号は、最低限覚える必要のあるものです。これ以外にも工程図記号はたくさんありますがここでは割愛します。
生産対象の物を中心に、原材料、部品などが製品化される過程を工程図記号で表して調査・分析する手法
加工、運搬、検査、停滞の工程図記号を用いて、工程の流れを記述し分析する。
作業者を中心に、製品化される過程を工程図記号で表して調査・分析する手法
作業者工程分析は、作業台のレイアウトや作業手順の改善のために行われることが多い。
流れ線図を用いて、物や人の流れを把握し無駄な動きを分析する方法
流れ線図とは、建物の配置図に工程図記号を記入したもので、各工程図記号の位置関係を示すことができる。
工場で生産する際の、物の移動を効率化するための分析。
| 運搬分析 | 運搬工程分析 |
|---|---|
| 運搬活性分析 | |
| 空運搬分析 |
活性示数を用いて、運搬状況を分析するもの
対象品の移動のしやすさ、置き方や荷姿を分析、検討するための方法。
活性示数とは、移動するための4つの手間(まとめる、起こす、持ち上げる、持って行く)のうち、省かれている数。値が大きいほど良い。
| 状態 | 活性示数 |
|---|---|
| 床にバラ置き | 0 |
| 箱に入れた状態 | 1 |
| パレットに乗った状態 | 2 |
| 台車に乗った状態 | 3 |
| コンベアで動いてる状態 | 4 |
人や運搬機器のみ移動させる状態を減らすための分析
人や運搬機器のみの移動を空運搬といい、空運搬係数を用いて分析が行われる。空運搬係数は理想的には0が好ましいが、現実的には2以下にすることが一般的。
[mathjax] $$空運搬係数=\frac{空移動距離}{物の移動距離}$$マテリアルハンドリングのことで、物の移動、積み込み、積み下ろし、取り付け、取り外しなど物の取り扱いのこと
経験則などから得られた改善事項をマテハンの原則(運搬の原則)という
| マテハンの原則 | 内容 |
|---|---|
| 活性荷物の原則 | 品物を動かしやすい状態に保ち、無駄を排除しようとするもの。 パレットやユニットロードの活用など |
| 直線化の原則 | 運搬経路は極力直線(一方向に物が流れる)にしようというもの。 |
| スペース活用の原則 | 床へのバラ置きをなくし、スペースを有効活用しようというもの。 箱やパレットの活用など |
| 継ぎ目の原則 | 移動の継ぎ目(次の移動までの間)で載せ替えや再取り扱いなど無駄な手間を無くそうというもの。 |
| 自重軽減の原則 | 運搬具の自重を減らそうというもの。 |
作業者が行う全ての動作を調査、分析し、最適な作業方法を求めるための手法。このような常に作業方法の改善を心掛けることをモーションマインドという。
| 動作研究 | 作業系列 | 連合作業分析 |
|---|---|---|
| 動作研究 | サーブリック分析 | |
| 両手動作分析 |
身体の動かし方、工具の使い方などの基本動作の法則で、この原則に則った仕事は経済的であるという考え
| 動作経済の原則 | 内容 |
|---|---|
| 動作方法 | 両手は同時に使う 腕は左右対称に動かす 重力や慣性など自然の力を利用する etc |
| 作業場所 | 工具や材料は、作業者の手の届く範囲に配置する 工具や材料は、作業者の全面に配置する 工具や材料は、作業順序に合わせ配置する 椅子や作業台は適切な高さにする etc |
| 工具 | 専用の工具を使用する 1つ以上の工具は、できるだけ1つにまとめる 工具は握りやすい形状にする etc |
人と機械、2人以上の人が協同して作業を行うとき、その協同作業の効率を高めるための手法
人や機械の手待ち、停止ロス(機械干渉)を減少させ、効率化を図ることを目的とする。
ギルブレスが考案した、手作業を18種の作業に分類し分析する手法
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 第1類:必要な動作 | 手を伸ばす つかむ 運ぶ 組み合す 使う 分解する 放す 調べる |
| 第2類:作業を遅らせる動作 | 探す 見出す 位置決め 選ぶ 考える 前置き |
| 第3類:作業に不必要な動作 | 保持 休む 避けられない遅れ(故障など) 避けられる遅れ(寝るなど) |
価値を生む動作は、組み合す、使う、分解するのみ。
アメリカの経営技術士で動作研究の第一人者(1868年〜1924年)
第一次大戦中に軍に勤務した際、武器の組み立てを迅速に効率良く行うためにサーブリック分析を考案した。「サーブリック」はギルブレスの英語綴りを逆読みしたもの。
作業または、製造方法の実施効率の評価および標準時間を設定するための手法のこと。
| 作業測定 | 稼働分析 | ワークサンプリング |
|---|---|---|
| 連続観測法 | ||
| 時間研究 | ストップウォッチ法 | |
| 実績資料法 | ||
| 経験的見積り法 | ||
| 標準時間資料法 | ||
| PTS法 |
稼働分析とは、作業者や機械設備の稼働率を求める手法のこと。
$$稼働率=\frac{稼働時間}{総時間}$$
時間研究とは、作業を行うのに要する時間を測定する手法で、作業の効率化や標準時間の設定を目的とするものである。
作業者や機械のある瞬間の動作を記録・集計し、各作業の発生割合を統計的に分析する手法
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 記録、集計が容易 データの整理が容易 作業者が調査を意識することが少なくデータの信頼性が高い | あくまで統計なので詳細な分析には向かない サンプル数が少ないと信頼性が低くなる |
各作業の分類は以下のようになる。
| 作業分類 | 内容 |
|---|---|
| 準備段取作業 | 作業準備、工具の段取りなど。 |
| 主作業(主体作業) | 実質的な作業。 |
| 付随作業(主体作業) | 主作業に付随し規則的に発生。 材料、工具の取り付け、取り外しなど。 |
| 作業余裕(管理余裕) | 主作業を行うための不規則に発生する作業。 機械の調整、掃除、材料の運搬など。 |
| 職場余裕(管理余裕) | 作業管理のために不規則に発生する作業。 打合せ、機械の故障など。 |
| 疲労余裕(人的余裕) | 休憩など。 |
| 用達余裕(人的余裕) | トイレ、食事、汗拭きなど。 |
作業内容を継続的に観測する方法
ワークサンプリングと反対に、詳細な分析が可能だが観測やデータの整理が煩雑で、作業者が調査を意識し不正確なデータとなる恐れがある。
その仕事に適性を持ち習熟した作業者が、所定の作業条件のもとで、必要な余裕を持ち、正常な作業ペースによって仕事を遂行するために必要とされる時間
標準時間の設定方法として以下がある。
| 手法 | 適する作業 | 精度 |
|---|---|---|
| ストップウォッチ法 | サイクル作業 | 高い |
| 実績資料法 | 特注品の生産など個別生産で、繰り返しの少ない作業 | 低い |
| 経験見積り法 | 個別生産で、繰り返しの少ない作業 | 低い |
| 標準時間資料法 | 共通する要素作業の多い作業 | 高い |
| PTS法 | 短サイクルで、繰り返しの多い作業 | 高い |
以下の手順で標準時間を算出する。
$$標準時間=正味時間+余裕時間$$
| 用語 | 算出式 |
|---|---|
| レイティング | 観測時間を基準とする作業時間と比較、評価しレイティング係数正味時間を算出する方法 $$レイティング係数=\frac{基準とする作業ペース}{観測作業ペース}\times100$$ 正常なペースを100とする。 ・レイティング係数 > 100:作業が速い人 ・レイティング係数 < 100:作業が遅い人 |
| 正味時間 | 主体作業、準備段取作業を遂行するために直接必要な時間 $$正味時間=観測時間 \times レイティング係数$$ |
| 余裕時間 | 作業を遂行するために必要と認められる遅れの時間 |
| 余裕率 | 標準時間もしくは正味時間に占める余裕時間の割合 【内掛け法】 $$余裕率=\frac{余裕時間}{正味時間+余裕時間}\times100$$ 【外掛け法】 $$余裕率=\frac{余裕時間}{正味時間}\times100$$ |
過去の作業日報などの実績資料を基に標準時間を見積もる方法
個別生産や特注品など繰り返しの少ない作業に適した方法。手間やコストが少ないが、精度が低い。
熟練工などの過去の経験則から標準時間を見積もる方法
個別生産や特注品など繰り返しの少ない作業に適した方法。主観的な方法のため精度にバラツキが出る。
共通的な作業項目ごとに所要時間を資料化し、それらを合計することで標準時間を算出する方法
標準時間を算出するための資料をまとめるのに手間がかかる。
作業をサーブリック分析により微動作ごとに作業時間を合計し標準時間を算出する方法
微動作レベルでは作業者間で個人差がなくレイティングを必要としないが、専門的なスキルを必要とする。
中小企業診断士1次試験の運営管理に頻出の論点として、IE(インダストリアルエンジニアリング)の頻出用語についてまとめました。
ここで記載した内容は基本的な事項のみです。記載した内容以外にも出題論点はたくさんあるので、過去問や問題集を繰り返し解き、応用力を高めるようにしましょう。
中小企業診断士の1次試験「運営管理」の効率的な勉強方法については、別記事で詳細解説しているのでこちらも参考にしてください。
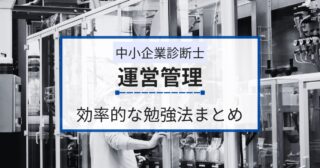
コメント