受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
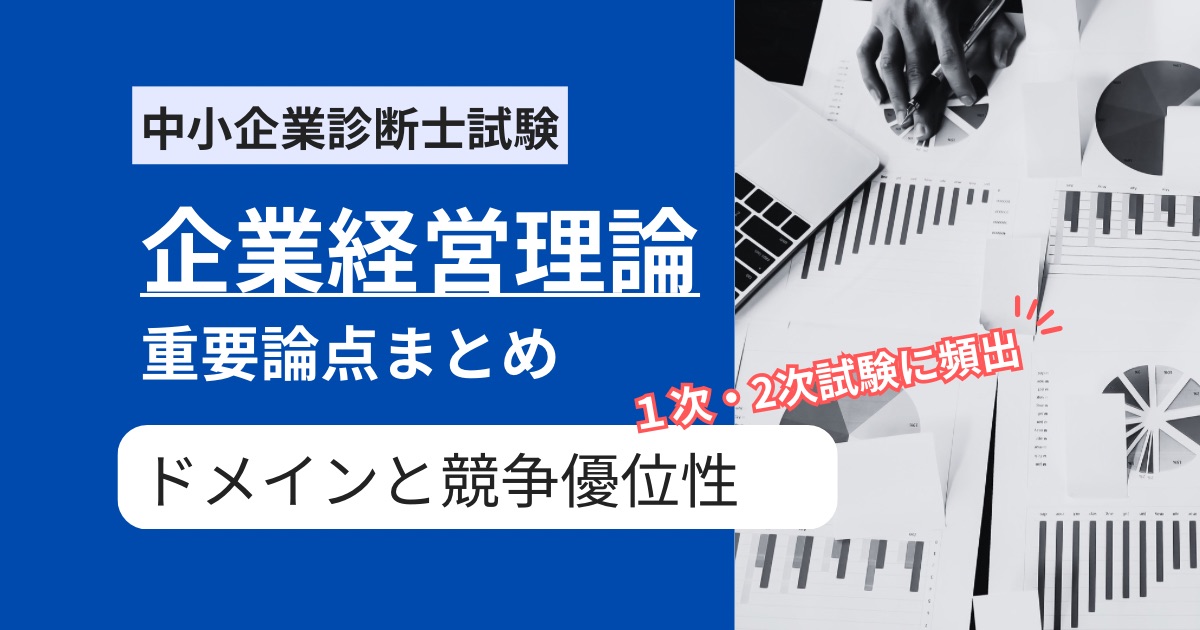
中小企業診断士試験の一次試験(企業経営理論)によく出る、ドメインと競争優位性に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
企業経営理論全般に言える話ですが、用語の暗記だけでは解答が難しく、より深い理解が求められます。また、問題文に抽象的な表現が多いので、ある程度の慣れが必要です。
過去問を繰り返し解き、問題文に慣れ、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例Ⅰ、事例Ⅱでドメインや経営戦略が問われます。
各用語が直接問われることはないですが、事例企業の経営戦略上の助言をする上で、ドメインや競争優位性などをしっかりと理解しておく必要があります。
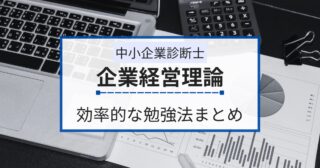
ドメインとは、企業が行う事業のあるべき姿、方針を明示したもの。ドメインの設定が狭いと、顧客ニーズに合わなくなる。また、ドメインの設定が広いと、経営資源の分散、競争に巻き込まれることになる。
モノ(製品やサービス)を中心にドメインを定義する
事業ドメインが明確になるが、定義された製品やサービス以外のモノを作りづらく、事業展開の柔軟性が低くなるという特徴がある。
顧客のニーズを中心にドメインを定義する
事業の拡大が容易、だがターゲットや製品が不明確となることがある。
全社レベルの方針やあるべき姿を定義したもの
事業の範囲、事業ポートフォリオを規定、企業のアイデンティティを規定する。事業ドメインの集合が企業ドメインとなる。
事業レベルでの方針を定義したもの
具体的に、どのようなターゲットにどのようなニーズを満たしていくかを規定する。単一事業の企業は、事業ドメイン=企業ドメイン となる。
ドメインを定義するフレームワークとして、1980年にデレク・エーベルが提唱したモデル
競争優位性の源となるもの。
他社にマネできない、顧客に利益をもたらす、自社の技術、スキル、ノウハウ
競合他社がマネすることが困難であること。
模倣困難性が高いと競争優位性が高い。資源の希少性やノウハウなどの情報資源があげられる。物理的な経営資源と比べ、ノウハウや専門スキルなどの情報的経営資源は模倣困難性が高い。
企業の競争優位性を経営資源から分析する手法
5つの競争要因から収益性を分析するモデル。
| 要因 | 競争要因 |
|---|---|
| 内的要因 | 供給業者の交渉力 |
| 買い手の交渉力 | |
| 既存業者間の敵対関係 | |
| 外的要因 | 新規参入業者の有無 |
| 代替品の有無 |
供給業者が寡占、独占的技術を持つ場合、その供給業者に依存することで、業界にとっては収益性を悪化させる脅威となる
例えば、
PC業界では、インテル、マイクロソフトなどのPCのコアとなるCPUやOSの技術・供給で圧倒的な力を持つため、PC本体の製造メーカーはそれに依存せざるを得ない。
音楽プレイヤーでは、Apple、Sonyなどが圧倒的なブランド力を誇るため、それらに従属せざるを得ない。
買い手(ある業界の製品を販売する顧客)が、大規模な流通網を持ち購買力が非常に大きい場合は、業界にとって収益性を悪化させる脅威となる
例えば、
セブンイレブンなど大手コンビニチェーンは大規模な流通網を持つため、買い手側の交渉力は強大となりメーカなど販売側はそれに依存せざるを得ない。
価格競争となり収益性を悪化させる原因となる
以下の場合、価格競争となり収益性を悪化させる原因となりやすい。
参入障壁が低いと、業界内で同業者が多くなり収益性を悪化させる脅威となる
同機能の製品の登場により、既存製品の価値が下がり収益性を悪化させる脅威となる
例えば、
中小企業診断士 企業経営理論に頻出の、ドメインと競争優位性に関する頻出用語をまとめました。
ここでまとめた内容以外にも、出題される用語や論点はたくさんあるので、過去問を繰り返し解き応用力を養う必要があります。
また、企業経営理論の内容は2次試験の事例問題でも関連する用語や知識が必要になります。直接用語の意味を問われる問題は出題されませんが、企業経営理論の知識を前提として、事例企業の診断・助言をする必要があるため、用語の意味を人に説明できるレベルが求められます。
企業経営理論の効率的な勉強方法については別記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
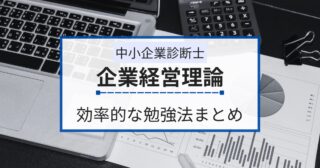
コメント