受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
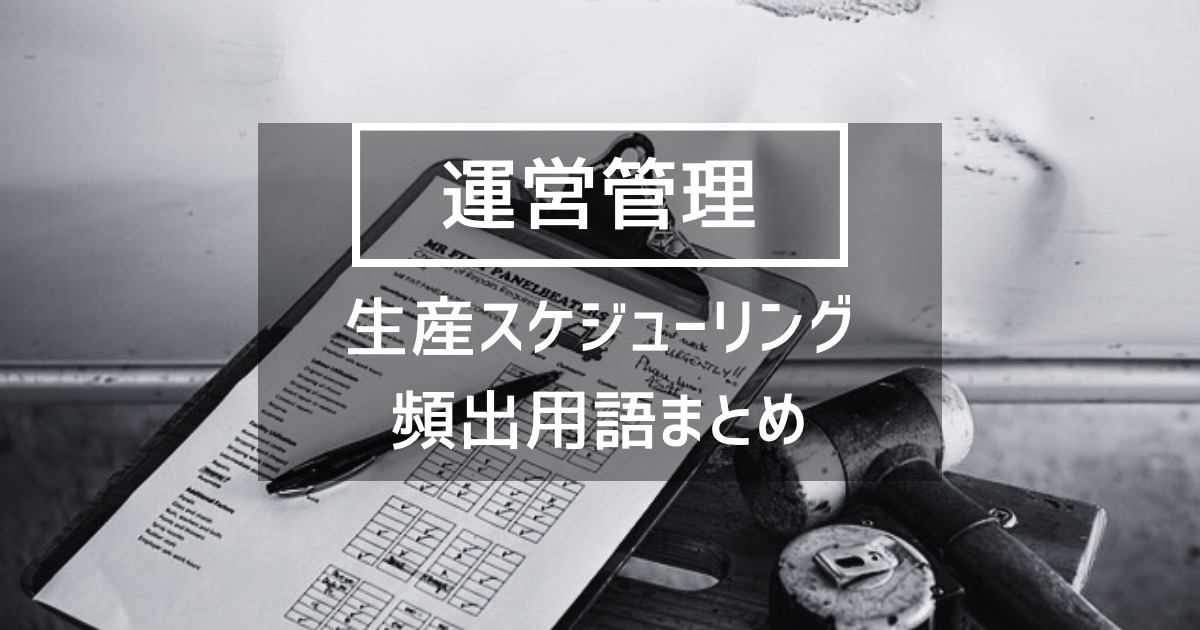
中小企業診断士試験の一次試験(運営管理)によく出る、生産スケジューリングと生産統制に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。図表の読み取りや計算問題が出題されることが多いので過去問や参考書で対策しましょう。
二次試験の事例Ⅲで生産管理に関する診断・助言の出題があります。
各用語が直接問われることはないです。ただし、このへんの用語を理解した前提で事例問題が問われます。ので、一次試験でしっかり知識を貯えておく必要があります。
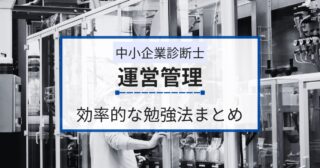
生産スケジューリングの定義は、「製品または部品の製造を行うにあたって、使用可能な資源の制約下で、製品または部品それぞれの工程ごとの着手時期・終了時期・着手順序・使用設備を決める活動のこと」とされている。
複数の製品を製造(ジョブ)する際に、全てのジョブで作業が類似で、作業工程と機械配置順序が同じ生産形態に対するスケジューリング
複数の製品の製造で、全ての工程が機械配置に沿って一方向に流れる。代表的なスケジューリングとしてジョンソン法がある。
2段階の工程に複数の製品(生産オーダー)が出ているときの、作業期間が最短となる作業順序を決める手法。
ジョンソン法の算出方法は以下の通りとなる。
| 製品 | 工程1(時間) | 工程2(時間) |
|---|---|---|
| A | 4 | 5 |
| B | 15 | 12 |
| C | 10 | 1 |
| D | 11 | 7 |
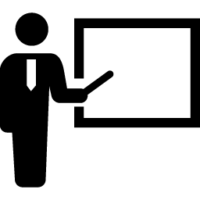
文字で書くとややこしいですが、実際に問題を解いてみると、すぐにできるようになります。過去問や問題集で練習してみましょう。
複数の製品を製造(ジョブ)する際に、ジョブにより作業工程と機械配置順序が異なる生産形態に対するスケジューリング
フローショップと比べ、ジョブの流れが複雑になるため、最適なスケジューリングは難しくなる。代表的な手法にディスパッチングルールがある。
ディスパッチングルール
待ちジョブの中から、次に優先して加工するジョブを決めるための規則
プロジェクトスケジューリングとは、複数工程のプロジェクトにおいて、プロジェクト全体の工程と個々の作業工程を管理する方法のこと。
ガントが考案した工程管理手法で、縦軸に各工程、横軸に時間を図示したもの
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 期間が視覚的に把握しやすい 進捗が視覚的に把握しやすい 全行程を網羅的に把握できToDoリスト的な機能がある | 大プロジェクトでは工程の前後関係の把握が困難になる 期間の短縮を考えるのに不向き |
アメリカの機械工学者、経営コンサルタント。
1910年にガントチャートを考案した。ガントチャート以外にも生産管理において、産業能率やTask And Bonusなどを考案した。
アローダイアグラムと呼ばれる矢印とノードを使ったスケジューリング手法
大規模かつ複雑なプロジェクトで用いられる。作業の前後関係の把握、クリティカルパスの把握が容易でプロジェクト全体の期間短縮を考えやすい。
ちなみにPERTは、1950年代にアメリカ海軍のミサイル開発にて考案された手法。
| アローダイアグラム | プロジェクトを構成している各作業を矢印で表し、作業間の先行関係にしたがって結合し、プロジェクトの開始と完了を表すノードを追加したネットワーク図 |
|---|---|
| クリティカルパス | 作業の遅れがプロジェクト全体の遅延につながる作業 |
見込生産を行う場合、需要予測を行い生産量を決定する。需要予測の代表的な手法に移動平均法と指数平滑法がある。
過去の実績値から需用量の予測を行う手法
移動平均法には、単純移動平均法と加重移動平均法の2つの手法がある。
| 手法 | 内容 |
|---|---|
| 単純移動平均法 | 過去の実績値の平均値を需用量の予測値とする方法 |
| 加重移動平均法 | 過去の実績値に重みを乗じ、その平均値を需用量の予測値とする方法 |
古い実績値ほど指数的に減少させた重み付けをした移動平均法
来月予測売上高 = 今月予測売上高 + α(今月実績売上高 ー 今月予測売上高)
生産統制とは、進捗管理や現品管理を行い、生産計画とのズレが生じている場合は、対応策(スケジュール見直し、材料の見直し、人員調整)を実施すること。
仕事の進捗状況を把握し、日々の仕事の進み具合を調整する活動
進捗管理の目的は、納期の厳守が第1にあり、次に仕掛品や在庫の調整がある。
資材、仕掛品、製品などの物について運搬・移動や停滞・保管の状況を管理する活動
どこに、何が、何個あるかを把握し、過不足がある場合は対応が必要となる。
各作業者・機械の負荷状態から余力の過不足を把握し、負荷を均等にさせる活動
負荷が能力以上にかかると納期を維持できなくなり、余力が大きいと遊休が生じてコストが増大することになる。
コメント