受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
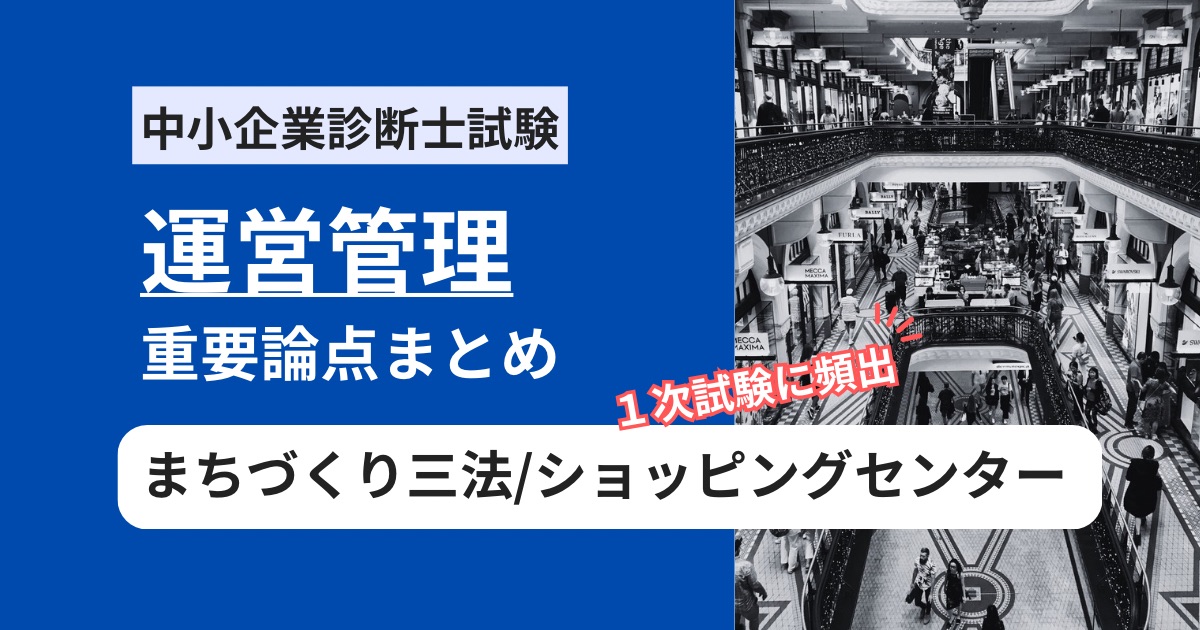
中小企業診断士試験の1次試験(運営管理)に頻出の、まちづくり三法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)の試験によく出るポイントを解説したいと思います。
よく出題されるとは言っても毎年1~2問程度です。法律なので全て覚えようとすると量が膨大で非現実的。重要なポイントをおさえて消去法で対応するのがベターです。
法律の改正があった場合は、その改正点が問われる可能性が非常に高いので確実に覚えるようにしましょう。
各用語が、直接問われることはありません。
二次試験の事例問題で法律に関して問われる問題はほとんど出ないので、1次試験の知識で十分対応可能です。
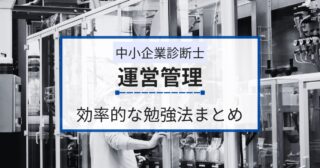
まちづくり三法とは、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法の3つの法律のこと。
| 年 | 大規模小売店舗立地法 | 中心市街地活性化法 | 都市計画法 |
|---|---|---|---|
| 平成10年 | 制定(旧法の廃止) | 制定 | 改正 |
| ↓ ↓ | 少子高齢化の加速 大型店の郊外出店が加速 中心市街地の空洞化 都市機能がスプロール的に拡散 | ||
| 平成18年 | – | 改正 | 改正 |
| ↓ ↓ | 都市機能の集約 コンパクトシティを目指す | ||
周辺地域の生活環境の保持を目的とし、大規模小売店舗を設置するものに対する規制を定めた法律
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 周辺地域の生活環境の保持 |
| 対象店舗 | 小売業(飲食店は含まれない) 店舗面積の合計が1,000㎡超 |
周辺地域の生活環境を保持するために、地方自治体により出店の調整を行う。対象店舗に対し、周辺地域の調査や住民への説明、質問回答、データの提示、責任体制の明確化などを求めるもの。
これにより大型店の郊外出店が加速し、中心市街地の空洞化、都市機能がスプロール的に拡散することとなった。
店舗面積の合計が1,000㎡超の小売業で、飲食店は含まれない。
店舗面積に含まれない部分:
階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、展覧会場、休憩室、公衆電話、便所、事務所、食堂、屋上
中小企業の保護を目的とし、大規模店舗(店舗面積500㎡超)の出店を規制するもの。平成10年に大規模小売店舗立地法が制定され廃止された。
中心市街地の都市機能の増進、経済力向上を目的とし、市町村が基本計画の作成、内閣総理大臣による認定、それに基づいた市町村に対する支援策を定める
中心市街地への来訪者増、小売業の売上増など効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)を経済産業大臣が認定する制度を創設。認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を行う。
特定民間中心市街地経済活力向上事業の要件
小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度を創設。認定を受けた事業に以下の支援、特例措置をとる。
大規模集客施設の郊外への出店を規制するなど、地域を用途ごとに区分けし都市計画の秩序を保つことを目的とする
都道府県が指定する区域で、自然や人口、交通量などから都市として整備する必要がある区域となる。
| 都市計画区域 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地となっている区域、及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制するべき区域 |
| 用途地域 | 12種類の地域区分をし、それぞれ建築可能な建物の大きさ・用途が定められた地域 |
| etc. | 他にもあり |
13種類の地域区分をし、それぞれ建築可能な建物の大きさ・用途が定められた地域
| 建築するもの | 可能な用途地域 |
|---|---|
| 延べ床面積1万㎡超の大規模集客施設が立地可能 | 商業地域 近隣商業地域 準工業地域 ※白地地域(用途地域の指定がない区域)は、原則不可 |
| 2階以下かつ床面積150㎡以下の店舗・飲食店 | 第一種低層住居・工業専用地域以外のすべて |
| 2階以下かつ床面積500㎡以下の店舗・飲食店 | 第一種 / 第二種低層住居・工業専用地域以外のすべて ※田園住居地域は、農家レストラン・農産物直販所など一定の店舗に限り建築可能 |
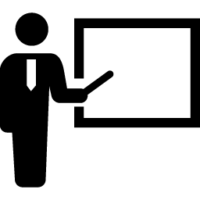
すべての用途地域を覚えようとすると、量が多く覚えるのが大変なので、まずは、よく問われる論点別に当てはまる用途地域を覚えると、頭に入りやすいと思います。※上記は一例です
一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう
上記の定義は、日本ショッピングセンター協会によるもの。また、同協会ではショッピングセンター(SC)として必要な条件を以下としている。
ショッピングセンターの概況についても、同協会に統計情報が掲載されている。(2022年末時点)
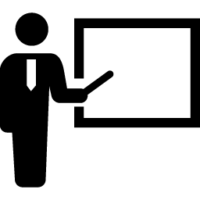
過去に統計データについて出題されたことがあります。データは毎年変わるので正確な数値を覚える必要はありませんが、大まかな数字や近年の概要を知っておく必要があります。
中小企業診断士1次試験の運営管理に頻出の論点として、まちづくり三法・ショッピングセンターの頻出用語についてまとめました。
ここで記載した内容は基本的な事項のみです。記載した内容以外にも出題論点はたくさんあるので、過去問や問題集を繰り返し解き、応用力を高めるようにしましょう。
中小企業診断士の1次試験「運営管理」の効率的な勉強方法については、別記事で詳細解説しているのでこちらも参考にしてください。
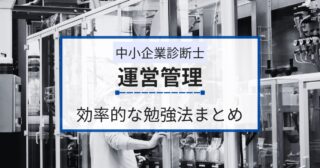
コメント