受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
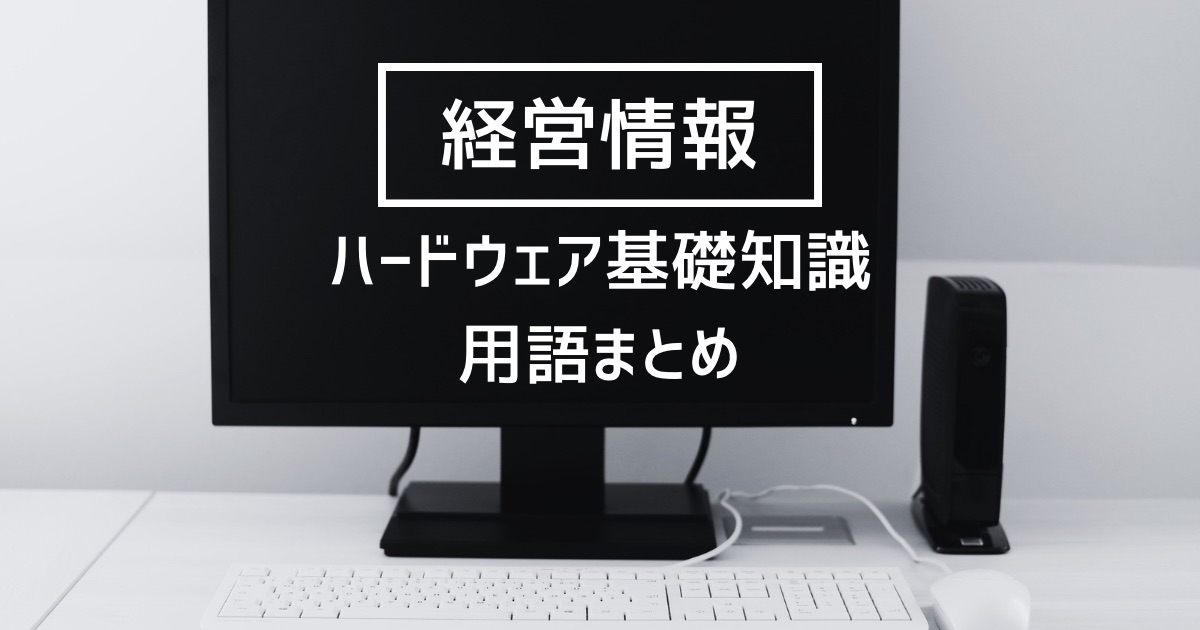
中小企業診断士試験の1次試験(経営情報システム)に頻出の、ハードウェアの基礎知識に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
経営情報システムは、技術進歩やトレンドにより出題内容や傾向が変わりやすいため、必ず最新の参考書や過去問を確認するようにしましょう。
経営情報システムは、2次試験とは基本的に無関連です。
ただし、近年の経営に情報システムは不可欠であるため、基本的な情報システムやトレンドなどが満たされた前提で問題が作成されています。
用語を問われることはありませんが、知識として押さえておく必要があります。
| 5大装置 | 内容 |
|---|---|
| CPU | 演算装置と制御装置 |
| 主記憶装置 | 一時的にプログラムやデータを保存する装置(メモリ) |
| 補助記憶装置 | 長期的にプログラムやデータを保存する装置(ハードディスク、SSDなど) |
| 入力装置 | 人がコンピュータに指示を送る装置(マウス、キーボード、タッチパネルなど) |
| 出力装置 | コンピュータで処理された情報を人が理解できる形で表示する装置(ディスプレイ、プリンタなど) |
CPUや記憶装置を装着する基盤
CPUやメモリは製造メーカにより規格が異なる。
BIOS(バイオス)
コンピュータに搭載される上記のようなハードウェアを制御するソフト。電源起動時にマザーボード上のBIOSが起動し、その後にOSが読み込まれる。
データの伝送路
CPUや記憶装置などのデータのやり取りを行う電気信号(光)の回路のこと。
| バスの種類 | 内容 |
|---|---|
| 内部バス | CPU内部のデータ伝送路 |
| 外部バス | CPUと記憶装置間の伝送路 |
| 拡張バス | 入出力装置を接続する伝送路 |
バスの構成
コンピュータの演算処理や制御処理を行う
コンピュータが送る信号の数
単位はHz(ヘルツ)で、値が大きいほど処理が高速になる。
1命令を実行するのに必要な平均クロック周期数
値が小さいほど処理が高速になる。
1秒間に実行可能な命令数
1MIPS = 1秒間に100万命令
1秒間に実行可能な浮動小数点演算の数
CPUの命令に対し並行処理を行い高速化を図る技術
複数のCPUを搭載し並列処理を行う構成
1つのCPUに複数のコアプロセッサを搭載したCPU
| 記憶装置 | 種類 |
|---|---|
| レジスタ | CPU内部 |
| キャッシュメモリ | SRAM |
| 主記憶装置 | DRAM |
| ディスクキャッシュ | DRAM |
| 補助記憶装置 | HDD、SSD、DVDなど |
CPU内部の一時的な記憶装置
主記憶装置のデータの一部を蓄え、CPUとデータのやり取りを行う
揮発性のSRAMを用い、高速処理が可能なため、CPUと主記憶装置の速度ギャップを埋める役割がある。
平均読み出し時間
平均読出時間 = キャッシュメモリのアクセス時間 × キャッシュヒット率 + 主記憶のアクセス時間(1 - キャッシュヒット率)
CPUが処理を行うためのデータを一時保存する記憶装置
揮発性のDRAMを用いる。一般的なメモリがこれに当たる。
主記憶装置と補助記憶装置の速度ギャップを埋めるためのメモリ
ハードディスク、もしくは主記憶装置の一部に設けられる。
データを長期間保存するための記憶装置
ハードディスクやSSDがこれに当たる。
複数の磁気ディスクからなら大容量な記憶装置
フラッシュメモリを用いた記憶装置
HDDと比べデータの読み書きが高速で、消費電力も少なく、耐衝撃性も高い。
半導体を用いた記憶媒体
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 不揮発性メモリ | 電源を落としてもデータを保持するメモリ |
| 揮発性メモリ | 電源を落とすとデータが失われるメモリ |
電源を落としてもデータを保持する不揮発性のメモリ
| ROMの種類 | 特徴 |
|---|---|
| マスクROM | データの書き換え不可、PCのリカバリー領域など |
| PROM | 一度だけ書き込み可能、CD-Rなど |
| EEPROM | 電気的にデータの消去が可能、フラッシュメモリ、USBメモリなど |
電源を落とすとデータが失われる揮発性メモリ
| RAMの種類 | 特徴 |
|---|---|
| DRAM | 低価格 低速 リフレッシュが必要 主記憶装置に用いられる |
| SRAM | 高価 高速 リフレッシュが不要 キャッシュメモリに用いられる |
| VRAM | 画面表示に必要なデータを保持するメモリ グラフィックボードに用いられる |
補助記憶装置の一部を主記憶装置として使う技術
主記憶装置の容量以上のデータを保存可能になる。
スワッピング
主記憶の使われないデータを仮想記憶に退避させ、必要なデータを主記憶に読み込むこと。
スワッピングが多発すると処理速度が低下(スラッシング)するため、主記憶装置の増設を検討する必要がある。
主記憶装置上の未使用領域を開放すること
メモリに並列アクセスを可能にする技術
誤り訂正符号により、誤ったビットを自動的に訂正する技術
人が理解する情報をコンピュータが理解できる情報に変換する装置
コンピュータで処理された情報を人が理解できる情報情報に変換する装置
装置と装置をつなぐ技術のこと
1本の線に1ビットずつ伝送する方式
パラレル伝送と比べ、高速。
例)USB、IEEE1394、SATA、e-STA、など
複数の線に同時に複数のビットを伝送する方式
シリアル伝送と比べ、低速。
例)SCSI、IDE
電源を切らずにインターフェイスの抜き差しが可能なもの
OSがデバイスを自動検知し、インターフェイスなどの設定が自動的に行われすぐに使用可能な状態になる技術
コメント