受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
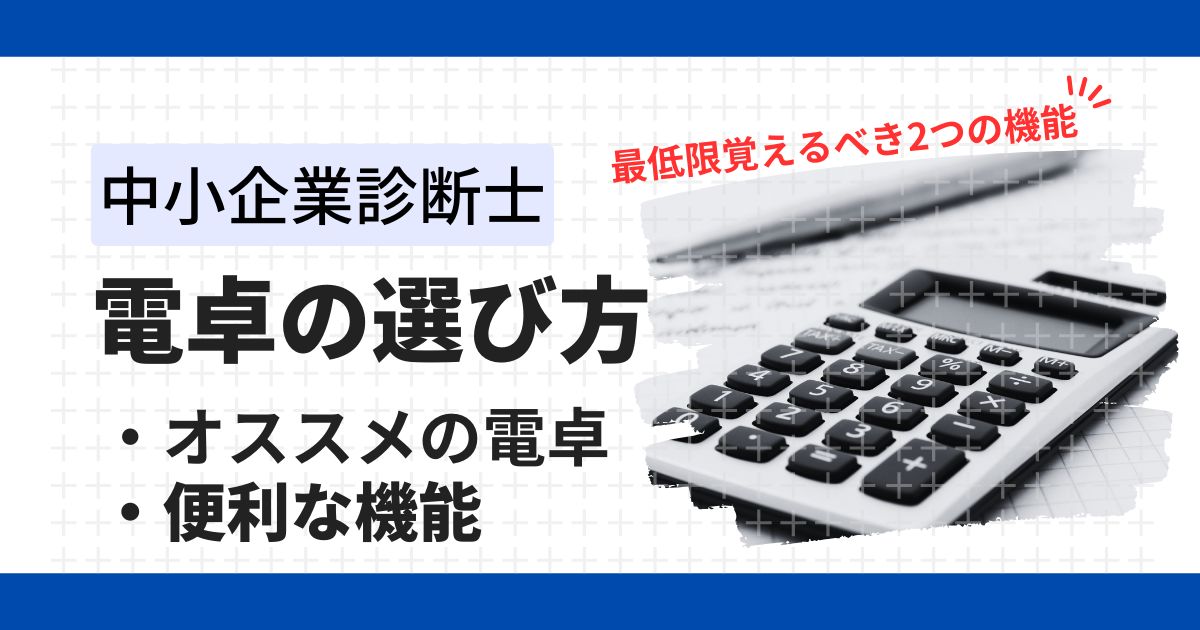
中小企業診断士試験でおすすめの電卓を知りたい、どんな機能が必要かよく分からないと思っていませんか。
中小企業診断士の2次試験では、電卓の持ち込みが認められています。それは、事例Ⅳの財務・会計において計算問題が出題されるためです。(1次試験は電卓の持ち込み不可)
2次試験の問題は、値が割りきれず、桁数が多い計算をする必要があり、電卓がないと計算することができません。
電卓なら何でも良いと言うわけではなく、持ち込める電卓の条件があるのと、使いやすさや最低限必要な機能があります。
電卓の機能に使い慣れると、2次試験の事例Ⅳの計算スピードが倍増しました。
電卓は長時間使っていると愛着もわいてくるので、気に入った使いやすい電卓を選ぶのがオススメです。
この記事では、中小企業診断士2次試験で持ち込むおすすめの電卓を紹介したいと思います。また、問題を正確に素早く解くための最低限覚えておいた方が良い電卓の使い方も合わせて解説します。
受験歴5年診断士
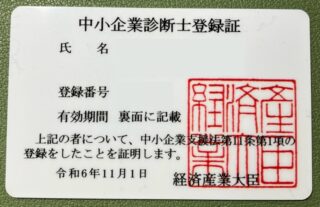
まずは、中小企業診断士の2次試験で持ち込む電卓の選び方を紹介したいと思います。
以下の電卓は試験に持ち込みが不可です。
持ち込み可能な範囲で大きめの電卓を選びましょう。
サイズの指定はありますが、試験会場で大きさを測られているのは見たことがありません。常識の範囲内ということだと思います。
あまりに小型の電卓は打ちづらく、入力ミスや転記ミスの原因になります。また、表示できる桁数も少なくなるため、ある程度大きめサイズの電卓がオススメです。
2次試験の事例問題では、億円単位の計算をする場合が多くあります。なので8桁までしか表示できない電卓だと計算ができなくなってしまいます。
桁数は12桁以上を表示できる電卓を選びましょう。
後述の使い方でも紹介しますが、NPVの計算など足し算と掛け算が混ざった計算を解く場面が多くあります。
$$NPV=CF_1\times\frac{1}{1+r}+CF_2\times\frac{1}{(1+r)^2}+・・+CF_n\times\frac{1}{(1+r)^n}-設備投資額$$
「GT(グランドトータル)」や「メモリ」機能がないと、掛け算の結果を紙に転記し最後に足し合わせる必要が出てきます。(小数点以下など桁数が多く、転記と再入力は苦行です、、、)
「GT」「メモリ」機能があれば、このような転記の必要がなく、時間短縮と転記ミスを減らすことができます。
「0」を2つ同時に入力できるボタンです。
地味な機能ですが、桁数の多い問題を解く際に、素早く入力することができ計算時間の短縮をすることができます。
無くても問題はありませんが、あると便利なボタンです。
次に、どの電卓を選べば良いか、オススメの電卓を紹介したいと思います。
中小企業診断士試験に必要な道具は別記事でも紹介していますが、電卓は試験が終わったあとの実務でも使用するので、長く愛用できるものを選ぶと良いかと思います。
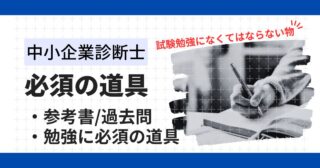
キーが打ちやすく、計算状態を表示する機能もある王道の電卓です。銀行員など計算を多くするプロにも愛用され、簿記や中小企業診断士など資格受験者の間でも多くの人が使用しているようです。
お値段は少し高いですが、長く使用できるのと、勉強のモチベーションアップにもなると思います。
お手頃なお値段なのが無印良品の電卓です。私はこれの黒を持っていますが、今は白しか売っていないようでした。
シンプルなデザインが良いという方はオススメです。大きめサイズで12桁表示可能、最低限必要な機能も揃っています。
続いて、中小企業診断士の2次試験(主に事例Ⅳ)のために最低限覚えておいた方が良い電卓の使い方を紹介します。
細かい操作やキーは機種・メーカー毎に異なるので、必ず取り扱い説明書を読むようにしましょう。
「GT(グランドトータル)」は、「=」を押した答えを自動的に記憶し、総合計を求めてくれるメモリ機能です。
使い方は簡単で、複数の計算をし最後に「GT」を押すだけです。
| 順番 | 入力キー | 液晶表示 |
|---|---|---|
| ① | 5 × 10 = | 50 |
| ② | 5 × 20 = | 100 |
| ③ | 5 × 30 = | 150 |
| ④ | GT | 300 |
GTメモリの消去は「CA」を押すと消えます。
メモリ機能も、GTと同じく計算結果をメモリに記憶させることができるのですが、GTとの違いは引算もできる点です。
使うキーは、「M+」「M-」「MR」「MC」の4つです。
次の式を計算する場合、(5 × 6) + (5 × 7) - (5 × 8) = 25
| 順番 | 入力キー | 液晶表示 |
|---|---|---|
| ① | 5 × 6 M+ | 30 |
| ② | 5 × 7 M+ | 35 |
| ③ | 5 × 8 M- | 40 |
| ④ | MR | 25 |
「MC」を押すと、メモリーに記憶されている数値が消去されます。
2次試験の事例Ⅳでは、以下のようなNPV計算やCVP分析の問題が出題されます。
$$NPV=CF_1\times\frac{1}{1+r}+CF_2\times\frac{1}{(1+r)^2}+・・+CF_n\times\frac{1}{(1+r)^n}-設備投資額$$
桁数が多く(10桁とか)絶対に割りきれません。メモリ機能がないと掛け算のたびに紙に転記し足すときに再入力する必要があり、時間が掛かるのと、計算ミスの元になります。
メモリ機能が大活躍するので、過去問や演習問題を解く際に電卓でメモリ機能を使い、使いこなせるようしておきましょう。
中小企業診断士の2次試験で持ち込む電卓の選び方とオススメ機種、最低限覚えておいた方が良い使い方を紹介しました。
他にもいろいろ機能はありますが、「GT」と「メモリ機能」は良く使うので覚えておきましょう。とりあえずこの2つの機能だけでも使いこなせると計算スピードは格段に早くなります。
電卓を使いこなせると、2次試験 事例Ⅳの計算スピードが格段にアップしました。
私の中小企業診断士 2次試験事例Ⅳの結果と、出題内容や再現答案は、別記事でまとめているのでこちらも参考にしてください。
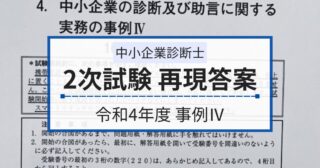
最後に、電卓は2台持ちをオススメします。
機械なので故障する可能性があります。実際に私は落として液晶が割れました。。。貴重な試験勉強の時間を浪費してしまうのと、試験当日に故障すると苦労が水の泡になってしまいます。
そして2台持つ場合は、同じ機種が良いです。電卓は機種によってキー配置や操作が異なるので、使い慣れるまでに少し時間がかかります。
可能な限り、同じ機種の電卓を2台持つことをオススメします。
コメント