受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
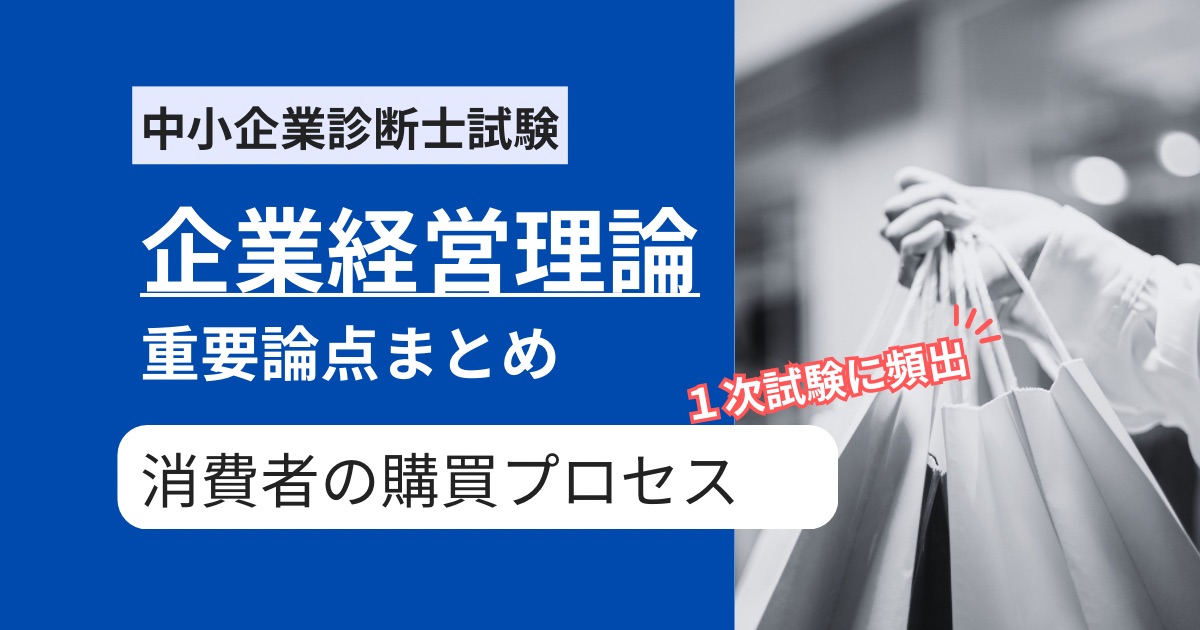
中小企業診断士試験の一次試験(企業経営理論)によく出る、消費者の購買プロセスに関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、1~2問ほど出題されます。
企業経営理論全般に言える話ですが、用語の暗記だけでは解答が難しく、より深い理解が求められます。また、問題文に抽象的な表現が多いので、ある程度の慣れが必要です。
過去問を繰り返し解き、問題文に慣れ、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例Ⅱで、マーケティングの課題が扱われます。
直接用語が問われることはありませんが、消費者の購買プロセスを前提とした診断・助言を問われることがあります。
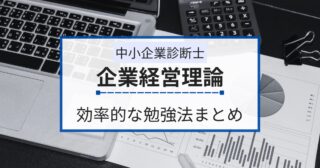
ものには有形財(商品)と無形財(サービス)がある。それぞれに消費財と産業財に分類される。
消費財は消費者が家庭で使うもの、産業財は企業が業務用に資材とした使うもの。
| 消費財の種類 | 内容 |
|---|---|
| 最寄品 | ・近所で買うもの ・低価格 ・購買頻度が高い 雑誌、洗剤、石鹸、たばこなどなど |
| 買回品 | ・比較して買うもの ・やや高価格 ・購買頻度が低い 衣類、家電製品、ホテルなど |
| 専門品 | ・高価格 ・購買頻度が低い 高級自動車、高級腕時計など |
| 非探索品 | 製品の認知度や知識が低いもの 生命保険など |
コトラーは、消費者が購買の意思決定に至るプロセスを5段階で定義している。
消費者が商品を認知してから購入するまでの購買行動のモデル。
消費者が商品を認知してから購入するまでの購買行動のモデル。
消費者がニーズを認知すること。
ニーズを認知した消費者が情報探索を行う。情報探索に影響を与える要素として以下が挙げられる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 関与 | 消費者の製品に対するこだわりの度合い |
| 知識 | 消費者が過去に体験したことがある製品やサービスの知識 |
| 口コミ | 製品やサービスに対する消費者同士の情報交換や共有。意思決定の後半段階の方が影響が大きく、悪い口コミほど影響は大きい。 |
| 準拠集団 | 消費者の行動に影響を与える集団。準拠集団の影響を受けるのは、高級品・公的な製品。逆に必需品・私的な製品は影響を受けにくい。 |
情報探索で得た製品について、代替え可能な製品を比較検討する。
代替品評価の結果、最も評価の高い製品を購買する。
消費者の期待と購買した内容が合致すれば満足し、期待に沿わなければ不満足を感じる。
消費者の期待が高すぎる場合、十分な水準を満たした製品であっても不満足を感じることが多い。
消費者が購買を決定する場合、購入する製品や消費者の特性により3つのタイプに分類できる。
| タイプ | 内容 |
|---|---|
| 定型的 | 製品に精通し、どのようなブランドが流通しているか知っている。こだわりはないがいつも同じブランドを購入することが多い。 製品:最寄品 価格:低価格 購買頻度:高 購買労力:少 |
| 限定的 | 製品に精通するが、どのようなブランドが流通しているか知らない。 製品:買回品 価格:中 購買頻度:中 購買労力:中 |
| 拡大的 | 製品についても流通するブランドについてもよく知らない。 製品:専門品 価格:高価格 購買頻度:低 購買労力:多 |
抵抗なく購入するブランドを変える行動のこと
例えば、飲料や菓子などがあげられる。
企業などが行う購買行動には、一般の消費者と異なり以下の特徴がある。
中小企業診断士 企業経営理論に頻出の、消費者の購買プロセスに関する重要用語をまとめました。
ここでまとめた内容以外にも、出題される用語や論点はたくさんあるので、過去問を繰り返し解き応用力を養う必要があります。
また、企業経営理論の内容は2次試験の事例問題でも関連する用語や知識が必要になります。直接用語の意味を問われる問題は出題されませんが、企業経営理論の知識を前提として、事例企業の診断・助言をする必要があるため、用語の意味を人に説明できるレベルが求められます。
企業経営理論の効率的な勉強方法については別記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
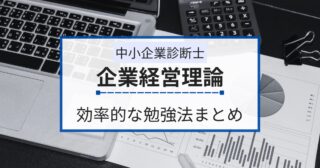
コメント