受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
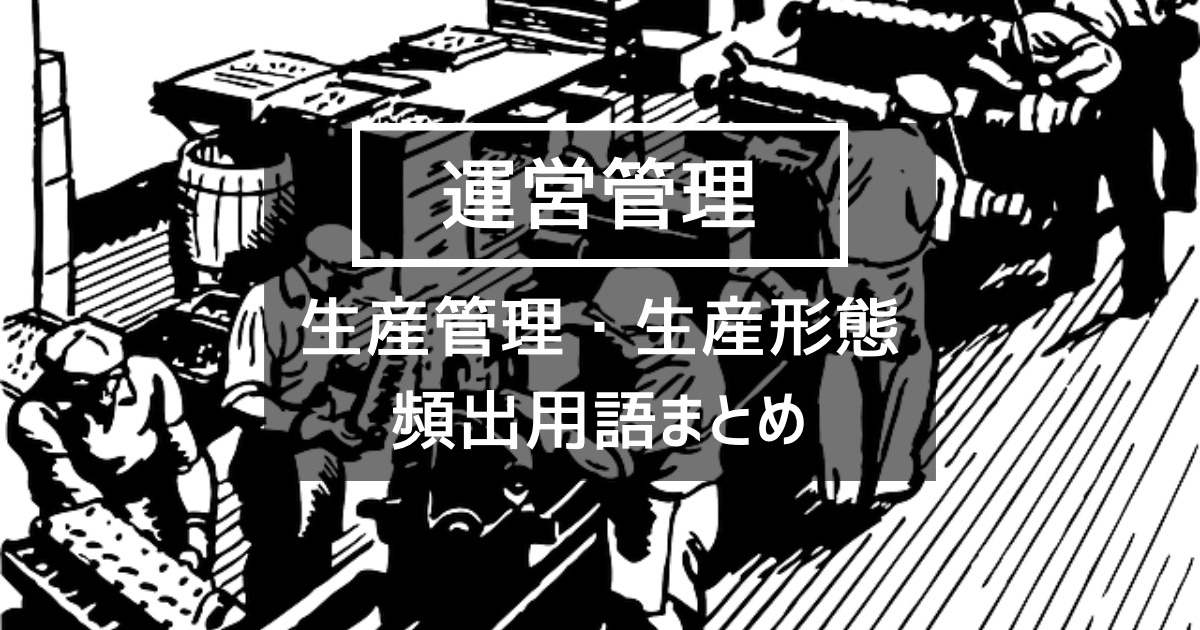
中小企業診断士試験の一次試験(運営管理)によく出る、生産管理に関する用語をまとめてみました。
ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるのと、ここの知識は二次試験の事例Ⅲで必ず問われるので、各用語の内容まで理解しておく必要があります。
毎年、数問出題される頻出論点で、毎年、同じ用語が問題を変え繰り返し問われることもあります。
二次試験の事例Ⅲで必須の知識です。
事例Ⅲたは製造業がテーマとなり、事例企業の生産上の問題・課題の指摘や改善策の助言をすることになります。生産管理の基本的な用語を理解していないと、対応が難しくなります。
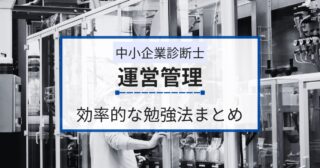
生産管理とは、Q(Quality:品質)、C(Cost:原価)、D(Delivery:納期)に関する最適な管理を行うもの
投入量に対する産出量との比率
[mathjax]$$生産性=\frac{産出量}{投入量}$$
生産管理の目標や評価の指標
以下の7つに着目したもの。
| PQCDSME | 内容 |
|---|---|
| Productivity | 生産性 |
| Quality | 品質 |
| Cost | 原価 |
| Delivery | 納期 |
| Safety | 安全性 |
| Morale | 意欲 |
| Environment(or Ecology) | 環境性 |
生産管理でQCDを満たすために運用するもの
| 生産の4M | 内容 |
|---|---|
| Material | 原材料、部品 |
| Machine | 機械設備 |
| Man | 作業者 |
| Method | 作業方法 |
生産の合理化における基本原則
| 3S | 内容 |
|---|---|
| Simplification | 単純化 (生産の簡略化をし生産効率を向上させる) |
| Standardization | 標準化 (作業の容易化、原価低減を行う) |
| Specialization | 専門化 (企業の専門性を高める) |
職場の管理の前提となる整理、整頓、清掃、清潔、躾のこと
| 5S | 内容 |
|---|---|
| 整理 | 不必要なものは捨てる |
| 整頓 | 必要なものを直ぐに使えるようにする |
| 清掃 | きれいにする |
| 清潔 | 整理、整頓、清掃を維持する |
| 躾 | ルールを守る |
工程、作業、動作に対する改善の4原則
二次試験の事例Ⅲで、作業行程に問題がある場合、このECRSの原則で検討・改善策をアプローチすることができます。
| ECRSの原則 | 内容 |
|---|---|
| Eliminate | 排除(なくせないか) |
| Combine | 結合(一緒にできないか) |
| Rearrange | 交換(順序を変えれないか) |
| Simplify | 簡素化(簡単にできないか) |
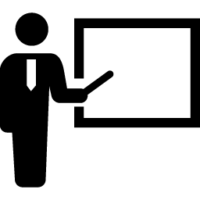
当時受講していた予備校の先生の教えで、「な・い・じゅ・か」と呪文のように覚えました。
改善活動を行うときに用いられる、what何を、whenいつ、who誰が、whereどこで、whyなぜ、howどのように、による問いかけ
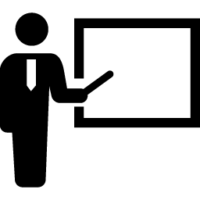
二次試験のテクニック的な話で、5W1Hや主語述語をしっかりと意識して回答を作成すると、読みやすい(採点者に伝わりやすい)文章になります。
度数率、年千人率は災害の発生頻度を表し、強度率は発生した災害の大きさを表す
| 安全性指標 | 内容 |
|---|---|
| 度数率 | 労働時間100万時間あたりに発生する死傷者数 $$度数率=\frac{死傷者数}{延べ実労働時間数}\times1,000,000$$ |
| 年千人率 | 労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数 $$年千人率=\frac{年間死傷者数}{平均労働者数}\times1,000$$ |
| 強度率 | 労働時間1,000時間あたりの労働損失日数 $$強度率=\frac{延べ労働損失日数}{延べ実労働時間数}\times1,000$$ |
1人または2人以上の作業者が複数台の機械を受け持って行う作業のこと
多行程もち作業と多台もち作業がある。
作業者が複数の工程を受け持つ作業のこと
工程ごとの時間のバラツキを柔軟に吸収することが可能。ただし、1人あたりの作業範囲が広くなるため多能工の育成が必要。
作業者が工程ごとに複数の機械を受け持って行う作業のとこ
作業者の受け持ち台数が多くなると機械干渉がおき作業効率が低下する。
機械干渉
1つの機械のメンテナンスを行なっている間、他の機械の稼働が停止すること。
投入された原材料の量に対し、産出された製品の量の割合
$$歩留り(\%)=\frac{製品の量}{原材料量}\times100$$
アパレル業で60%、プラスチック加工業で97%ほどと言われている。不良品の数も含む。
生産される製品のうち、不良品を除いた製品の比率
手直しを必要としない製品のみを評価するため、歩留まりよりも厳格な評価を行うことができる。
発注されてから納入されるまでの時間。素材が準備されてから完成品になるまでの時間
一般的にリードタイムは、ある工程に着手してから工程が完了するまでの時間とされるが、JIS規格では上記のように定義される。(JIS Z 8141-1206)
生産の着手時期から完了時期に至るまでの時間
次工程のための準備作業(工具の取替え、機械のメンテナンスなど)のこと
生産工程において、ロットサイズが小さいほど段取替えの回数が増え、生産性が低下する。
| 段取替え | 内容 |
|---|---|
| 内段取 | 機械を停止して行う |
| 外段取 | 機械を停止しない |
| シングル段取 | 機械の停止時間が10分未満の内段取 |
| 生産タイミング | 生産方法 | 品種 |
|---|---|---|
| 受注生産 | 個別生産 ロット生産 | 多品種少量 |
| 見込生産 | 連続生産 ロット生産 | 少品種多量 |
顧客が定めた仕様の製品を生産者が生産する形態
注文を受けてから生産開始する形態で、同じものを複数個必要としない大型の製品(造船・家・マンションなど)や企業の基幹システムなどがある。
生産者が市場の需要を見越して企画・設計した製品をせし、不特定な顧客を対象として市場に出荷する形態
受注する前に生産し在庫を抱えるため、需要予測の精度向上が重要となる。
個々の注文に応じて、その都度1回限りの生産を行う形態
標準化されない製品や生産に多大なコストと時間が掛かるものを生産する形態で、船舶や建造物、専用機械設備など。
品種ごとに生産量をまとめて複数の製品を交互に生産する形態
ロットサイズ
1ロットあたりの生産量。ロットサイズが小さくなるほど段取替えの頻度が増える。
同一の製品を一定期間続けて生産する形態
生産方法が標準化され、設計変更の少ない製品に適する。日用品、飲料など。
多くの品種を少量ずつ生産する形態
個別生産の形態をとることが多い。
少ない品種を大量に生産する形態
ライン生産とも呼ばれ、連続生産の形態をとることが多い。
コメント