受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

中小企業診断士試験の1次試験(運営管理)によく出る、資材管理と在庫管理に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題されている頻出論点です。発注方式の特徴と公式を覚える必要があります。特に計算問題は得点源になるので、確実に回答できるようにしましょう。
事例Ⅲ「生産・技術」で在庫管理に関する論点がよく出題されます。
用語を理解した前提で事例問題が問われるので、1次試験でしっかり知識を貯えておく必要があります。
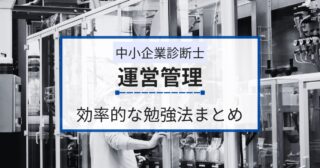
Material Requirements Planning(資材所要量計画)と呼ばれる、製品に必要な構成部品の正確な必要量を決めるシステム
MRPにより資材管理を標準化する目的として以下があげられる。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 品質向上 | 品質のバラツキ、不良品の削減、製品品質向上 |
| 原価低減 | 資材をまとめて発注することで単価の引き下げ |
| 在庫削減 | 資材種類の削減、共通化による在庫量削減 |
| 納期短縮 | 部品切れなどが少なくなり顧客納期遅れが削減 |
| 生産性向上 | 発注業務の負荷が軽減 |
デメリットとして、MRPにより資材管理の標準化を進めることで、新たなニーズへの柔軟性の欠如や、設計作業の複雑化をまねく恐れがある。
構成部品表(Bill of Material)のことで、各部品を生産するのに必要な子部品の種類と数量を示すリスト
BOMには表示形式の違いで以下の種類がある。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| サマリー型部品表 | 製造工程順序と関係なく、必要な部品とその総所要量の一覧表 |
| ストラクチャ型部品表 | 製造工程順序を考慮し、部品の親子関係を保ちツリー構造で表す部品表 |
また、BOMの使用場面の違いで以下の種類がある。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 設計部品表(E-BOM) | 製品を設計する際に作成する部品表。サマリー型部品表を用いることが多い。 |
| 製造部品表(M-BOM) | 製品を製造する際に作成する部品表。ストラクチャ型部品表を用いることが多い。 |
発注方式として代表的なものに、定量発注方式、定期発注方式、ダブルビン方式、補充点方式がある。
在庫量が発注点を下回ると、あらかじめ定められた一定量を発注する在庫管理方式
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 運用管理が容易 事務処理の効率化、自動化が可能 | 需要変動が激しいものに向かない 調達期間が長いものに向かない |
需要変動または補充期間の不確実性を吸収するために必要とされる在庫
急激な需要増や調達期間に在庫切れしないために備える在庫のこと。
$$安全在庫=k \times \sqrt{L} \times \alpha$$
発注を促す在庫水準
$$発注点=L \times \mu + 安全在庫$$
経済的発注量(EOQ)とは、総費用を最も小さくする発注量
あらかじめ定めた発注間隔で、発注量を発注ごとに決めて発注する在庫管理方式
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高精度の在庫管理が可能 需要変動の激しいものに対応可能 | 管理が煩雑 安全在庫が増加する可能性がある |
発注量=(在庫調整期間の予想消費量 - 現在の在庫量 - 発注残)+ 安全在庫
在庫を2つのビンに入れ片方のビンが空になったら、1つのビンの容量分の在庫を発注する方式
2棚法、2瓶法とも呼ばれる。
在庫が減った分だけ補充する在庫管理方式
補充点は最大在庫量となる。
在庫品目の取り扱い金額または量の大きい順に並べ、A、B、Cの3種類に分類し管理の重点を決めるのに用いる分析
パレートの法則を前提とし、ABC曲線(パレート図)により在庫品目をグルーピングする。
| A品目 | 金額割合の大きい品目の上位20%の品目。これだけで在庫金額全体の80%を占める。(パレートの法則) |
|---|---|
| B品目 | 品目数累計20〜50%の品目 |
| C品目 | 残りの50%の品目 |
各グループでの管理方式は以下となる。
| グループ | 発注方式 |
|---|---|
| A品目 | 定期発注方式 重点管理品目として欠品を避ける |
| B品目 | 定量発注方式 単価が高いものは定期発注方式をとる |
| C品目 | 定量発注方式 or ダブルビン方式 |
中小企業診断士1次試験の運営管理に頻出の論点として、資材管理(MRP)と在庫管理の頻出用語についてまとめました。
ここで記載した内容は基本的な事項のみです。記載した内容以外にも出題論点はたくさんあるので、過去問や問題集を繰り返し解き、応用力を高めるようにしましょう。
中小企業診断士の1次試験「運営管理」の効率的な勉強方法については、別記事で詳細解説しているのでこちらも参考にしてください。
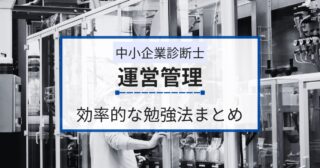
コメント