受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
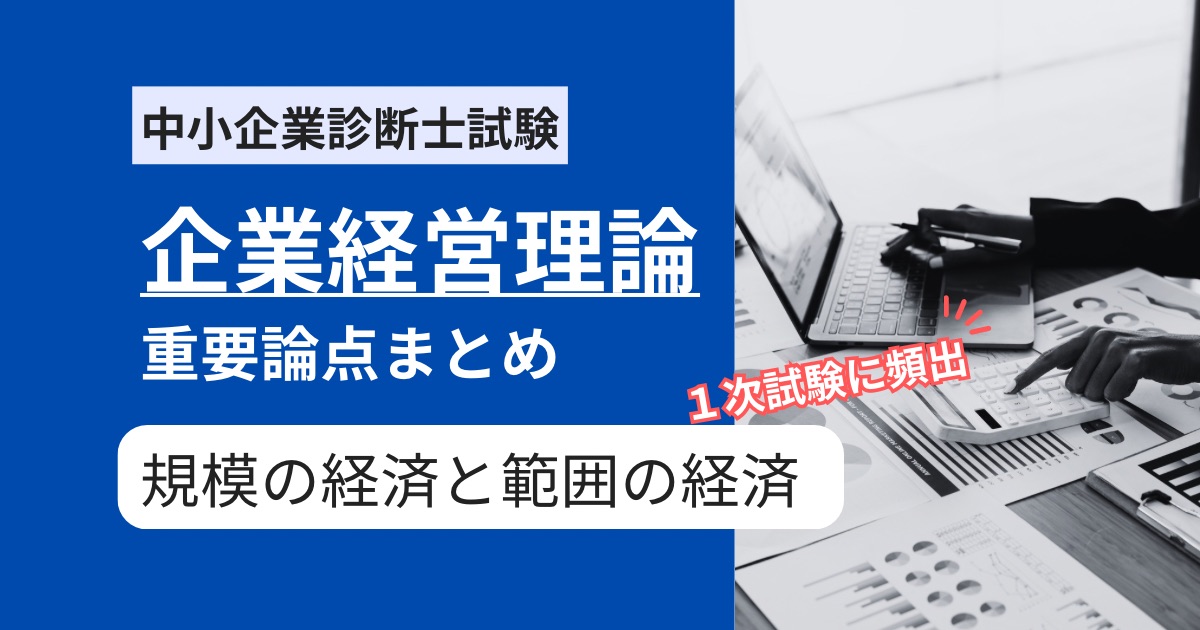
中小企業診断士試験の1次試験(企業経営理論)によく出る、規模の経済と範囲の経済の違いをまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
企業経営理論全般に言える話ですが、用語の暗記だけでは解答が難しく、より深い理解が求められます。また、問題文に抽象的な表現が多いので、ある程度の慣れが必要です。
過去問を繰り返し解き、問題文に慣れ、知識の定着と応用力を高めるようにしましょう。
事例ⅡやⅢで、マーケティング・生産の課題が扱われます。
事例企業の対象が中小企業なので、規模の経済や範囲の経済はあまり扱われないですが、基本的な知識として押さえておく必要はあります。
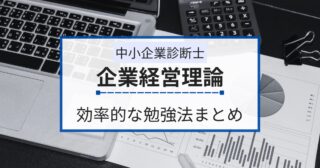
どちらもたくさん作って固定費の割合を少なくするコスト削減の話ですが、「規模の経済」は同じものを大量生産するのに対し、「範囲の経済」は多様な種類のものを作ることを指します。
| 規模の経済 | 同じものを大量生産することで、固定費の割合を少なくすること。 |
|---|---|
| 範囲の経済 | 事業の多角化等で多種多様なものを作ることで、既存の資源(設備・人材・ノウハウ)を有効活用し、固定費の割合を少なくすること。 |
企業の規模や生産量の増大に従い、製品1個当たりの平均コストが逓減すること
同じものを大量生産することで、生産コストへの投資以上の生産量を得られる事を言います。
規模の経済が働く業界では、新規参入企業は初期から大量生産する大規模な生産体制が必要で、初期コストが掛かるため大きなリスクとなり、参入障壁となります。
また、規模の経済が働く業界 → 差別化が難しい → 低価格競争 → 規模の経済を求めるという流れになる。規模=シェアの拡大を図るために、合併などによる業界の再編がなされることが多くなります。
規模の経済がはたらきやすい業界として以下のようの特徴があります。
例としては、
累積生産量の増加に従い、単位あたりの生産コストが逓減するとこ
製品の累積生産量が増えるに従い、経験による作業者の熟練、工程や設備の改善により製品1個当たりの生産コストを一定の割合で下げることができる。
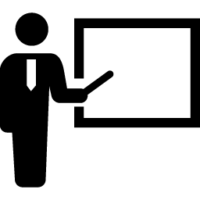
規模の経済と引っ掛けでよく出題されることがあります。
「規模の経済」は、ある時(導入期など)に大規模な生産体制を築くことで実現できるため静的なものに対し、「経験曲線効果」は時間軸(累積生産量)に従い実現されるため動的なものです。
規模の経済のメリットは、上述の通りコストの削減にあります。
反対にデメリットは、莫大な初期コストが掛かることと、大量生産による柔軟性に欠ける点です。
規模の経済を発揮するためには、大量生産するための設備投資が必要になります。また、同じものを大量に作るため、急な需要の変動への対応が難しくなります。売れなくなったときは大きな負債を抱えるリスクがあります。
また、同一製品を作るために業務の効率化を測ることになるため、日々変化する顧客にニーズや市場の変化に臨機応変に対応することが難しいという面があります。
規模が大きくなりすぎると、逆に管理コストの増大や固定費の増加という規模の不経済により単位あたりの生産コストが上昇することになります。
複数の製品や事業をそれぞれ別の企業が生産提供するより、同一企業で行う方がコスト削減が可能なこと
異なる製品で原材料・生産設備の共有や管理の一元化により、コストを削減でき、事業の多角化のメリットとしてあげられます。
具体的な例としては、
範囲の経済の代表的な例が「Amazon」です。書籍のネット販売から現在では総合ECサイトや様々なクラウドサービスまでを手掛けます。全てが自社の資源を有効活用し事業全体の効率化が図られています。
元々はオルガンなどの楽器メーカーでしたが、楽器製造技術を活かして音響機器、半導体、電子楽器、自動車部品やスポーツ用品など「多角化経営」を進めているのが特徴です。
エレクトロニクス、音楽・映画・ゲームなどエンターテインメント、金融等複数の事業を展開しています。分かりやすいのが、PlayStationブランドによる家庭用ゲーム機から、配信する音楽・ゲーム・映画までを手掛けることでシナジー効果を生み競争力を高めています
複数の事業を展開することで、Aの事業がBに良い効果をもたらし、Bの事業もAに良い効果をもたらすこと
シナジー効果(相乗効果)の例として、鉄道会社のスーパーマーケットや百貨店経営があげられる。(西武鉄道+西武百貨店、東急電鉄+東急ストアなど)鉄道会社がスーパーや百貨店を運営することで得られるメリットとして
同様に、鉄道会社によるレジャー施設の経営や、不動産開発もシナジー効果を狙ったものとなる。
範囲の経済のメリットは、上述したようにシナジー効果による自社資源の有効活用にあります。
反対にデメリットは、行き過ぎた多角化による管理コストの増大や自社資源の有効活用の限界が挙げられます。
複数のサービスや製品を扱うことで、品質管理や在庫管理は複雑化し、それらを管理するのに膨大なコストが掛かることになります。(範囲の不経済)
また、新たな事業で自社の設備や資産を有効活用できず新たな投資が必要になったり、リソースが分散することで競争力を高めるのが困難になるなど、シナジー効果を生むことができないことがあります。
中小企業診断士 企業経営理論に頻出の、規模の経済と範囲の経済の違いをまとめました。
ここでまとめた内容以外にも、出題される用語や論点はたくさんあるので、過去問を繰り返し解き応用力を養う必要があります。
また、企業経営理論の内容は2次試験の事例問題でも関連する用語や知識が必要になります。直接用語の意味を問われる問題は出題されませんが、企業経営理論の知識を前提として、事例企業の診断・助言をする必要があるため、用語の意味を人に説明できるレベルが求められます。
企業経営理論の効率的な勉強方法については別記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
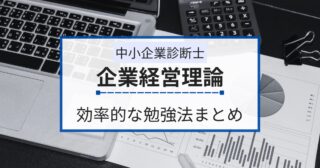
コメント