受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。
教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。
TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。
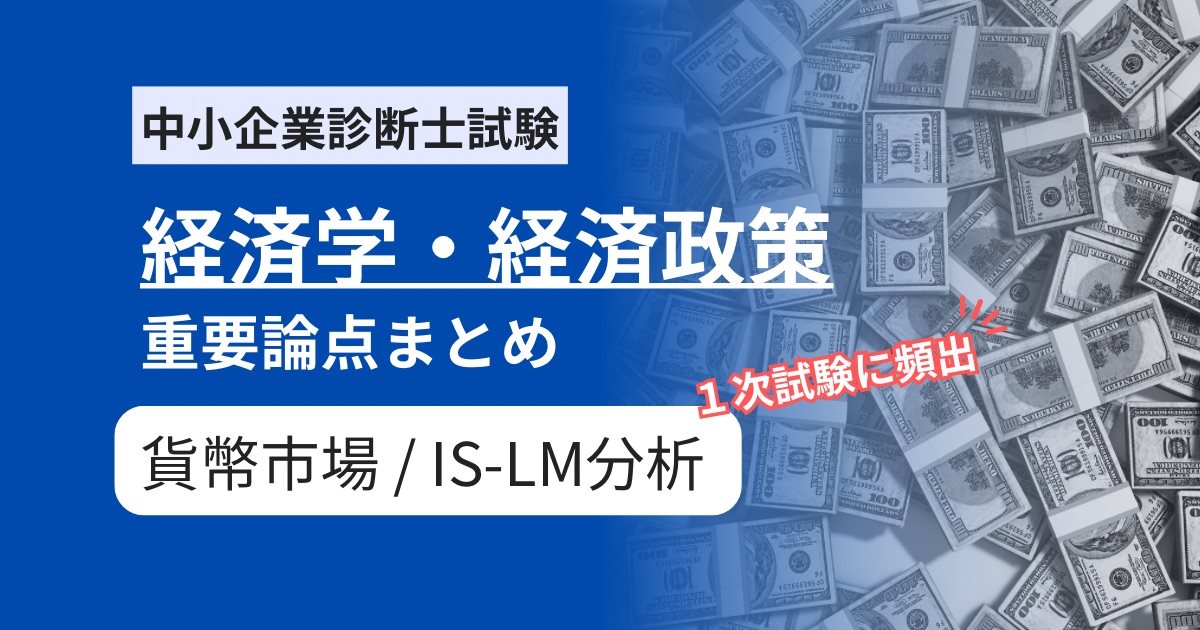
中小企業診断士試験の1次試験(経済学)に頻出の、貨幣市場の分析とIS-LM分析に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
計算問題やグラフの読み取り問題が多く出題されます。出題される論点は毎年変化をつけてくるので応用力が問われます。あまり深追いすると時間が掛かるので、まずは基本的な内容を押さえ過去問を繰り返し解き、どのような論点が出題されるか確認し応用力を高めるようにしましょう。
経済学は、2次試験とは無関連です。
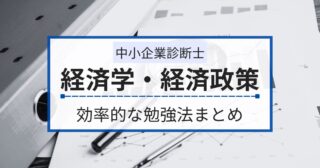
中央銀行(日銀)が直接供給する貨幣
流通現金+法定準備
法定準備とは、市中銀行が、預金のうち一定割合を中央銀行(日銀)に預ける事を義務付けられている準備金(中央銀行当座預金)のこと。金利はない。
マイナス金利政策
法定準備金を超える額の日銀当座預金には、金利が掛かる。この金利をマイナスにする政策のこと。
つまり、
日銀に預けると金利を取られる→マネタリーベースの増加を促す
信用創造により産み出された貨幣
流通現金+預金
マネーサプライがマネタリーベースの何倍になるかを表した数値
$$貨幣乗数=\frac{c+1}{c+r}$$
中央銀行(日銀)が債権の売買を行い、マネタリーベースをコントロールすること
| 公開市場操作 | 内容 |
|---|---|
| 売りオペ | 日銀が債権を売る ↓ 民間の現金減少 ↓ マネタリーベース減少 |
| 買いオペ | 日銀が債権を買う ↓ 民間の現金増加 ↓ マネタリーベース増加 |
取引総額と使われた貨幣総額は等しくなるという理論
MV(貨幣総額)=PY(名目国民所得)
マネーサプライの増加は物価を上昇させるだけで、拡張的金融政策は無意味となる。
貨幣供給量の増加率を国民所得の成長に合わせ毎年「k%」に固定し、あとは市場の自動安定化機能に任せるという考え
自動安定化機能(ビルトインスタビライザー)とは、自動的に経済を安定化させるように働く財政政策のこと。
例)累進課税、社会保障制度など
利子率により、貨幣を保有するか債券を保有するかを決定する
| 貨幣需要 | 内容 |
|---|---|
| 貨幣の取引需要 | モノを買うために貨幣を保有すること |
| 貨幣の投機的需要 | 安全資産で流動性の高い貨幣を保有すること |
貨幣市場で「国民所得 Y」と「利子率 i」の均衡点を表した曲線
| LM曲線 | 特徴 |
|---|---|
| 形状 | 右上がり 国民所得が増えると利子率が上がる |
| 傾き | 貨幣需要の利子率弾力性 大 → 緩やか 小 → 急 |
| シフト | 右シフト:貨幣供給量増加、物価低下→量的金融緩和政策 左シフト:貨幣供給量減少、物価上昇 |
| 曲線の上下 | 上側:超過供給 下側:超過需要 |
| 流動性のわな | 貨幣需要の利子率弾力性が無限大(利子率がゼロ) →LM曲線は水平になる |
IS曲線とLM曲線の交点を、均衡国民所得、均衡利子率とよぶ
| 財政政策 | 効果 |
|---|---|
| 拡張的財政政策 | IS曲線は右シフトする 均衡国民所得/利子率は増加する |
| 緊縮的財政政策 | IS曲線は左シフトする 均衡国民所得/利子率は減少する |
拡張的財政政策による利子率の増加が投資の抑制を起こし、国民所得の増加を押し戻すこと
| 金融政策 | 効果 |
|---|---|
| 拡張的金融政策 | LM曲線は右シフトする 均衡国民所得/利子率は低下する |
| 緊縮的金融政策 | LM曲線は左シフトする 均衡国民所得/利子率は増加する |
中小企業診断士1次試験の経済学に頻出の論点として、貨幣市場の分析とIS-LM分析についてまとめました。
ここで記載した内容は基本的な事項のみです。記載した内容以外にも出題論点はたくさんあるので、過去問や問題集を繰り返し解き、応用力を高めるようにしましょう。
中小企業診断士1次試験「経済学・経済政策」の効率的な勉強方法については、別記事で詳細解説しているのでこちらも参考にしてください。
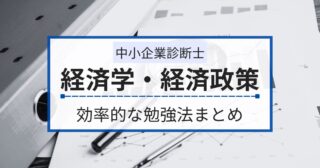
コメント